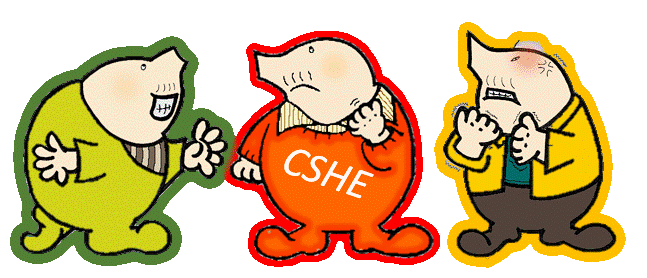高等教育グローサリー
高等教育グローサリー
高等教育にかかわる様々な用語を解説しています。
本センターの季刊紙『かわらばん』より「高等教育グローサリー(旧:カリキュラムグローサリー 」を随時転載していきます。
 掲載語一覧(あいうえお順)
掲載語一覧(あいうえお順)
- アイスブレイク(2015年冬号)
- アウトカム評価(2008年冬号)
- アカデミック・インテグリティ(2015年秋号)
- アカデミック・ライティング教育(2010年冬号)
- アクティブ・ラーニング(2013年春号)
- アドミッションポリシー(2007年秋号)
- 一文要約(2017年冬号)
- 移転可能なスキル(2008年夏号)
- 院生講師(2018年夏号)
- インフォーマル学習(2012年冬号)
- エクステンション(大学拡張/大学開放) (2020年春号)
- エンロールメント・マネジメント(2013年夏号)
- オープンサイエンス(2018年冬号)
- オナーズ・プログラム(2007年冬号)
- 学修時間(2012年夏号)
- 学修ポートフォリオ(2016年春号)
- 学習歴認定制度(2011年冬号)
- 学生エンゲージメント(2017年春号)
- 学生の研究体験(2011年夏号)
- 学期制(2013年秋号)
- 学校学習の時間モデル(2020年夏号)
- 科目番号方式(2006年夏号)
- 学問の自由(2020年秋号)
- カリキュラム(2006年春号)
- 基幹教員制度(2023年冬号)
- 機関別認証評価(2021年春号)
- キャップ制(2007年春号)
- キャリア教育(2009年夏号)
- 教育の内部質保証(2022年春号)
- 教員メンター制度(2010年春号)
- 教授会(2015年春号)
- 教職課程(2021年冬号)
- 共同学位制度(2008年春号)
- グループ試験(2014年秋号)
- 経験学習論(2012年秋号)
- コア・コンピテンシー(2007年夏号)
- コースパケット(2009年秋号)
- サイエンスショップ(2009年春号)
- 実務家教員(2020年冬号)
- サバティカル・リーブ(2016年秋号)
- サービスラーニング(2008年秋号)
- 奨学金(2019年秋号)
- 初習教育(2009年冬号)
- シンク・ペア・シェア(2014年夏号)
- STEM教育(2017年夏号)
- 成績評価点平均値(2006年秋号)
- 責任ある研究・イノベーション(2019年冬号)
- 専門職大学(2018年秋号)
- 大学設置基準(2022年秋号)
- 大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(FTE調査)(2019年春号)
- 大学の教科書(2011年春号)
- 多職種連携教育(2018年春号)
- 単位制度(2019年夏号)
- チューニング(2015年夏号)
- パフォーマンス評価(2016年夏号)
- 発問(2014年春号)
- 反転授業(2014年冬号)
- プレFD(2021年秋号)
- マイクロクレデンシャル(2022年冬号)
- マイクロティーチング(2010年秋号)
- ライティングセンター(2010年夏号)
- ラーニングアナリティクス(2017年秋号)
- ラーニング・コモンズの活用(2011年秋号)
- リカレント教育(2022年夏号)
- 履修系統図(2016年冬号)
- ルーブリック(2013年冬号)
 用語集
用語集
日本語で「教育課程」とも訳されるカリキュラム(curriculum)は、「自分の歩む進路、走路、流れ」を意味するラテン語のクレレ(currere)を語源にもつといわれています。カリキュラムは、ある教育機関の教育理念や目標を具体的な教育活動の全体計画として表したものであるといえます。学習の主体である学生にとっては、何がどの時期に学習できるのかを知るための枠組みであり、入学から卒業までの学習行動の指針になります。その指針は、単に時間割といった狭い意味に限定されません。個々のプログラムやコース、授業の枠組みを示すとともに、多次元にわたる学習内容と達成基準を含んだ空間的、時間的な広がりを持った地図のようなものです。
名古屋大学は学士課程の「四年一貫教育」体制を謳っています。その実現には、基礎教育および教養教育を担う全学教育の科目と専門教育を担う学部の科目のすべてが、教育目標の達成にむけて、学習者の視点から体系的にみえるように設計され、その設計思想が全教職員に共有されることが必要になります。そのためには、名古屋大学の教育にかかわる人たちが、まずはカリキュラムに関わる用語やシステムについて知っておくことが第一歩となるでしょう。
このコラムでは、そうした関連用語やシステムを「カリキュラム・グローサリー」としてご紹介し、名古屋大学におけるカリキュラムをめぐる対話の促進に役立ちたいと考えています。
(かわらばん2006年春号,鳥居 朋子)
北米の大学のシラバスや科目要覧などを手にしたとき、科目(授業)ごとに3ケタぐらいの番号や文字が付されていることに気づいた方は多いでしょう。「科目番号方式」は、それぞれの科目の提供母体(学科など)や専門の度合いを瞬時に識別できるよう、数字や文字等のコードによって科目を体系的に管理するシステムです。
大学によってコードの様式は異なりますが、通常、2潤オ4ケタの数字や、ときには数字と文字の組み合わせで表されます。たとえば、米国のサンフランシスコ州立大学では、以下のようなコード体系になっています。0潤オ99 補習教育および単位を授与しない科目、 100潤オ299 1、2年生が履修すべき科目、 300潤オ699 3、4年生が履修すべき科目、 700潤オ899 大学院課程の科目、 900潤オ999 連合博士課程の科目、 9000潤オ9999 成人教育部門における専門職業科目。一般に、数字が大きくなるにつれて、より専門性(必ずしも難易度ではない)が高くなるとみなされます。
科目番号方式は、単にカリキュラムの体系性の観点から個々の科目を管理運営することに有効なだけではなく、学生が履修に適切な科目を判別し、学習する際にも大いに役立ちます。また、ある科目を履修するための前提要件として、それまでに合格しておかなければならない科目や推奨する関連科目などを特定し構造的に可視化することにも有効性を発揮します。
学士課程の「四年一貫教育」を謳う名古屋大学は、9つの学部と13の研究科(大学院)、多数の附属施設や研究所などで構成されており、多様な学問領域を擁していることは明らかです。大規模総合大学としての豊かな学術的資源を最大限に活かしたカリキュラムを体系的に学生提供するためにも、科目番号方式の導入は一考に価するといえましょう。
(かわらばん2006年夏号,鳥居 朋子)
厳格な成績評価や単位の実質化をどう実現するか、という問題を最近よく目や耳にします。その方法をめぐって、各大学で活発な議論が展開されています。米国を中心に普及しているGPAは、学生の学修の到達度を明確にし、自らの学習設計を主体的に描かせ、意欲的な学習活動を促進することを目的とした成績評価方法です。具体的には、5段階(A・B・C・D・F)の成績評価をもとに、1単位あたりの成績評価点の平均値を算出します。一般的には、各科目の成績評定について、Aを4ポイント、Bを3ポイント、Cを2ポイント、Dを1ポイント、Fを0ポイントと換算し、以下の計算式が用いられます。
GPA={(科目χ1のポイント×単位数)+(科目χ2の・・)+・・・}/全科目の総単位数
日本でもすでにGPA制度を採用している大学の事例があります。たとえば、北海道大学では「秀・優・良・可・不可」の5段階の成績評価にもとづくGPA制度が導入されています。
また、米国の大学では、学生が奨学金を獲得するための基準として学期(セメスター)ごとのGPAを採用している事例が多くみられます。自らの学生生活を継続する上で、高いGPAを維持できるかどうかは、学生にとってもきわめて大きな関心事となっています。
従来、4段階評価(優・良・可・不可)が一般的であった日本の大学から、外国の大学への留学や大学院への進学を申請する際は、成績評価の読み替え等が必要となり、学生の送り手、受け手の大学双方に煩雑な作業が生じていました。名古屋大学では、毎年約1,200名の留学生が在籍し、なおかつ多くの交換留学生等を輩出しています。GPAを導入することにより、大学教育の国際化が促進される条件のひとつが整うといえるでしょう。研究だけでなく教育の国際水準も視野に入れて活動している基幹大学として、名古屋大学でのGPAの導入の是非も含め、成績評価方法の検討は急がれる課題のひとつなのかもしれません。
(かわらばん2006年秋号,鳥居 朋子)
20 世紀の初期に米国の大学ではじまったオナーズ・プログラム(優等生特別プログラム)は、英国の優等学位にならって設計されたと言われています。学士課程の中でも、成績優秀またはより専門性の高い学位に位置づけられる優等学位(honors degree)の取得を目指すプログラムです。受講生にはさまざまな特典(有名教授によるセミナーの優先受講権、各界の著名人を招いたセミナー兼昼食会への参加、有利な大学院進学条件、奨学金の優先支給など)が用意されています。選抜基準は、高校時代の成績や大学入学後の学業成績、本人の学習意欲の高さなど、大学や学部によってさまざまです。
オナーズ・プログラムは、優秀な学生、高い意欲を持った学生を集めて、かれらが切磋琢磨する機会を提供することに意義があると考えられています。たとえば、ミシガン大学アナーバー校文理学芸カレッジでは、通常のプログラムと別にオナーズ・プログラムのカリキュラムを提供しているだけではなく、学生の学習活動や宿舎も分けています。一方、ノースキャロライナ大学チャペルヒル校では、あえて別プログラムを設けず、通常のプログラムのなかで優等生に対しさまざまな選択肢や優遇措置を与える方式をとっています。どのような形態や方式をとるにしろ、学習意欲の高い学生の成長をより促すための教育機会として位置づけられています。
近年、日本の大学でも、独自の組織文化や文脈に合わせてオナーズ・プログラムの趣旨を採り入れ、学生の勉学意欲を励ますことを目的とした制度が多様な形で導入され始めています。たとえば、新潟大学では、「副専攻制度」としてオナーズ・プログラムを運用しています。同制度は、当該専門分野以外の特定分野科目を一定単位数以上取得した学生にその勉学の認証を付与する制度です。専門分野以外の分野について関心を持つ学生のモチベーションを組織的に高める仕組みだといえます。また、立命館大学経済学部では、2 年次以降に受講できる独自プログラムとして、高度な専門領域を集中的・系統的に学ぶプログラムを開講しています。
名古屋大学では、学士課程から修士課程へ進学する学生が全体の約5 割に達しています。「もっと高度な内容を学びたい」、「もっと専門性を深めたい」と考える学生たちの希望に応え、かれらの能力を最大限に引き出すためにも、名古屋大学にふさわしいオナーズ・プログラムのあり方を検討してみてはいかがでしょうか。
(かわらばん2007年冬号,鳥居 朋子)
近年、1 年間あるいは1 学期間に履修登録できる単位の上限を設けている大学が増加しています。この取り組みはキャップ制と言われています。文部科学省のデータによると、平成16 年度に国公私立429 大学がキャップ制を採用しています。これは全大学の約62 パーセントにあたります。
多くの大学でキャップ制が採用されている理由はどこにあるのでしょうか。文部科学省が毎年キャップ制の調査をしていることも理由の一つだと思われますが、それだけではありません。低学年次に学生が多くの授業を履修するため、学習が中途半端になっていると考えられているからです。学生は、できるだけ早期に単位を揃えたいと考えるようです。学生は高校までのすき間のない時間割に慣れています。また、卒業論文や就職活動のことを考えると余裕をもって高学年次に進みたいと考えているようです。このような学生の単位の早取り傾向を抑制し、個々の授業における学習を充実させるためにキャップ制が活用されています。
名古屋大学においても全学教育科目の早取り傾向が度々指摘されています。必ずしも今後キャップ制を全面的に導入する必要はありませんが、もし導入しようと考える場合には、次の2点に気をつけるべきでしょう。
第一に、キャップ制の導入が学生の学習を充実させるものにならなければなりません。単位の早取りの抑制は手段であって目的ではありません。キャップ制によって学生に生まれた時間が、学習活動ではないもののみに向けられていたらキャップ制の意味はありません。キャップ制の導入と同時に、個々の授業の授業時間外を含めた学習活動を充実させることが求められます。
第二に、キャップ制の導入が学生の多様な学習機会を奪わないかどうかを確認する必要があります。インターンシップ、教職課程、海外留学などを希望する学生にとって不利益となるような制度となってはいけません。また、学習意欲の高い学生にも配慮する必要があります。その対策として、キャップ制をGPA 制度と連動させ、成績の優れた学生には制限を超えて履修することを認めている大学もあります。
(かわらばん2007年春号,中井俊樹)
大学教育のなかでコア・コンピテンシーといえば、「この大学あるいはこの学部を卒業したからには、すべての卒業生が***の能力を身につけていますよ」と宣言し、学生もそれを自覚できるような中核的能力のことを指します。「***」に入るのは、場に応じて知識や技能を操作する能力だったり、課題を解決するにあたっての行動や思考の様式だったりします。北米の大学で重視されているコンピテンシーとしては、つぎのような能力が挙げられています。
- コミュニケーション(文章力、会話力、聴解力)・基礎数学
- コンピュータリテラシー ・紛争解決 ・批判的思考 ・倫理
- 対人関係 ・インタビュー ・基礎統計 ・学習スキル
- 問題解決 ・読解 ・情報活用 ・多文化理解 ・科学的思考
これらの能力の具体的な内容と獲得方法は、大学の文脈によって違います。日本の大学でも、コア・コンピテンシーを検討し、カリキュラムに反映させる動きが、見られるようになってきています。
ビジネスの世界でのコア・コンピテンシーは、すこし様子が異なります。ある企業がもつ、競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力、競合他社に真似できない製品・サービスを生みだすための核となる能力を意味するからです。ここでは、個人の能力ではなく、チームとしての能力が問われています。個人の能力が統合され、シナジーが起きた結果としてのチームの能力が、これまでにない成果を生み出せるかどうかが問われているのです。
それにひきかえ、大学におけるコア・コンピテンシーの議論は、卒業生ひとりひとりの能力に偏りがちです。社会に散在する卒業生たちが、ゆるやかに同窓の連携を保ち、市民社会の一員としての役割を果たせるように、という考え方もあって良いのではないでしょうか。また、教職員と学生・卒業生が一団となってどんな大学をつくれるのか、というところに、“大学自身の”コア・コンピテンシーを求めることもできるように思います。
(かわらばん2007年夏号,齋藤芳子)
アドミッション・ポリシーは、一言でいえば、大学における学生の入学受け入れ方針のことです。つまり、それぞれの大学が、入学後に教育を受けるために求められる能力(知識・スキル等)の内容や水準、適性等を明らかにするとともに、それを高校、生徒、父母に示すための文書のことです。
これが注目されるようになった直接のきっかけは、中央教育審議会の答申『初等中等教育と高等教育との接続の改善について』(1999 年12 月)です。かつては、大学入学に当たって入試の存在が大きく、大学側は多数の受験生の中からいかに効率的に適格者を選抜できる試験問題を作成するか、受験生の側は合格できるだけの学力をいかに獲得するかが重大な関心事でした。受験生が多く、競争率も一定水準以上に保たれている状況では、画一的な選抜方法はある程度有効であり、また必要でもありましたが、少子化とともに大学・短大進学率が50%に達する段階では、それだけでは不十分です。高校教育が多様化し、大学も機能・性格が多様化し入学者選抜方法も多様化(推薦入学・AO入試の普及等)している中で、学生が入学後に大学に適応し、教育を十分に受け、発達してゆくためには、大学が求めている能力・適性、入学者選抜方法などを正確に受験生に伝えることが必要になります。その前提として、それぞれの大学がどのような教育を提供できるのか、教育の結果として学生はどのような能力が獲得できるのか、どのような進路が可能になるのか等を示すことが必要になります。教育目標やカリキュラムと表裏一体の関係にあるのが、アドミッション・ポリシーなのです。
なお、大学評価ではアドミッション・ポリシーも評価対象になります。たんに策定しているかだけでなく、それに基づいて入学者選抜が適切に実施されているか、実質的に機能しているか、実施状況を検証するとともにその結果を入学者選抜の改善に役立てているかなども評価されます(大学評価・学位授与機構の「大学評価基準」)。そのため、サイクルを意識した明確なアドミッション・ポリシーを策定することが求められています。
(かわらばん2007年秋号,夏目達也)
大学卒業までに学生が身につけるべき学習成果の設定や、その測定・評価が俄かに注目を集めるようになりました。昨年の中央教育審議会で、出口管理による学士号取得者の質保証を目的に、「学士力」という言葉が生まれたのをご記憶の方も多いことでしょう。大学教育の重点が、「教授学習が行われる」という行為ではなく「教授学習によって、どのような知識やスキルや態度が身に付いたか」という学習成果にあることが強調されたと言えます。
このような学習成果の評価は「アウトカム評価」と呼ばれています。英米においては、プログラムに対してもコースに対しても「学習成果(learning outcomes)」を用います。いっぽう、日本語の「アウトカム評価」は学士課程プログラムを対象とすることが多いようです。当然ながら、評価する内容(学習成果)は、カリキュラム編成の時点で定めておくことになります。具体的な学士課程の学習成果として、先の中央教育審議会では、専門分野の知識・技能に加え、異文化理解、論理的思考力、チームワーク等々が挙げられました。
ここで考えなければならないことは、異文化理解、論理的思考力、チームワーク等々のスキルをいかに測るか、ということだけではありません。質を保証する「学士力」とは、おそらく、最低限の基準を提示するものになるでしょう。基準にプラスされる成果とは何か。その成果のためには、どのように教育したら良いのか。それらを疎かにして「学士力」ばかりに集中すれば、似たような人材ばかりを大量に養成することになりかねません。ひいては、大学教育の価値を大学人自ら低めることになってしまわないでしょうか。 「アウトカム評価」という用語が定着しつつあるなか、大学教育の意義や目標を折に触れて思い返す必要があるようです。
(かわらばん2008年冬号,齋藤芳子)
提携する2 つの大学が共同して学位を授与する制度を共同学位制度といいます。学生の側から見れば、同時ないし連続して2 つの大学に在籍することにより、複数の学位を取得できることになります。英語ではジョイントディグリーと呼ばれ、類似語としてダブル・ディグリー、デュアル・ディグリー、ツイニング・プログラムなどとも呼ばれています。
中央教育審議会は、共同学位について「近年の学問分野の学際化、融合化や、幅広い知識と柔軟な思考能力をもつ人材など社会における求められる人材の多様な要請などに対応する手段として」有効な方策としています。(※1)日本では、以前からいくつかの大学が海外の大学との間で共同学位を授与してきました。文科省調べでは、2005 年度段階で導入している大学は国立6,公立1,私立13 の計20 校、検討中の大学も同18、1、35 の計54 校あります。(※2)提携先から学生を受け入れる「受入型」、学生を派遣する「派遣型」、両者をあわせた「受入派遣型」に分類され、国立では「受入型」と「受入派遣型」、私立では「派遣型」と「受入派遣型」が、それぞれ半数を占めています。
共同学位が注目される背景には、世界各国の大学の国際化が急速に進むなかで、教員の共同研究、単位互換、学生移動といった大学間交流が活発になっていること、卒業・修了後に国際的に活躍できる能力を学生に習得させる一手段として活用できること等の事情があります。
共同学位が趣旨どおりに機能するためには、連携する大学間で教育目的・目標を明確にし、単位制度やカリキュラムの調整を図ることや、教育の質を保障するシステムを作ることが欠かせません。ちなみにボローニャ・プロセス(※3)を進めるEU 諸国では、共通の単位制度(ECTS)が採用され、各国間で教育の質の調整が図られています。共同学位制度を比較的導入しやすい環境になってきていると言えるでしょう。
※1 中央教育審議会大学分科会大学院部会『大学院部会における審議経過の概要-国際的に魅力ある大学院教育の展開に向けて-』(2004年8月)
※2 文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」(2007年)
※3 ヨーロッパ高等教育圏構築に向けて、ヨーロッパ諸国の学位制度の共通化を図る改革を指す。
(かわらばん2008年春号, 夏目達也)
英国リサーチカウンシルズは、その資金援助を受ける大学院生について、研究指導を通じて習得することが期待される技能(スキル)をまとめた声明「大学院生のスキル訓練要件に関する共同声明(Joint Statement of the Research Councils’Skills TrainingRequirements for Research Students)」を発表しています。この声明では、研究上のスキルやテクニックの訓練が大学院生の能力開発の中核であると前文に述べられたうえで、以下のようなスキルの提示がなされています。
(A)研究のスキルとテクニック:批判的思考・分析、概念作成、研究手法、専門分野のトレンド把握、経過の文書化、など
(B)研究環境の理解:研究倫理、関連規程、研究資金、研究評価、研究成果の応用・波及、など
(C)研究管理:プロジェクト管理、資源や機器の効果的な利用、情報管理と情報公開、など
(D)個人的態度・資質:知識習得の意欲、独創性、柔軟性、自己認識、自制心、イニシアティブ、など
(E)コミュニケーション:目的に適った文章、相手にあわせた手法、研究成果の正当性の主張、理解増進、他者の学習の支援、など
(F)ネットワーキングとチームワーキング:ネットワーク構築と維持、自己の役割と影響の理解、フィードバックと応答、など
(G)キャリア・マネジメント:継続的能力開発、雇用可能性の改善、就職機会の発見、自己表現、など
これらのスキルは、まずは博士学位論文を完成させるために、ひいては研究者として成功してゆくために必要不可欠なものです。しかし、研究者にならずとも、起業したり、政策立案に携わったり、物書きになったりと、博士の活躍できる場面は広がってきました。そして、そのような場面においても上記のスキルが有効であることから、「移転可能なスキル(transferable skills)」という呼び名が定着しています。研究を通じて身に付けうるスキルの幅広さを、ぜひ、日本の大学院生にも伝えていきたいと考えています。
(かわらばん2008年夏号, 齋藤芳子)
大学教育における体験的な学習の一つとして、サービスラーニングという形態があります。サービスラーニングには多様な定義がありますが、中央教育審議会の答申では、「社会の要請に対応した社会貢献活動に学生が実際に参加することを通じて,体験的に学習するとともに,社会に対する責任感等を養う教育方法」と定義されています。サービスラーニングの具体的な内容としては、市役所、児童保育施設、農業施設、海外のNGO において業務を体験する実践過程と、その実践過程を挟む事前学習と事後学習から構成されます。特にサービスラーニングでは、事後学習において体験をふりかえり学習効果を高める作業が重視されています。
このようなサービスラーニングは、1980 年代からアメリカの多くの大学で導入され、1100 以上の大学から構成されるキャンパスコンパクトというサービスラーニングを推進する全米組織も設立されています。日本においても、サービスラーニングを企画・実施するためのセンターや部署を立ち上げる大学が増えてきました。初期の頃は、大学のミッションとしてサービスを重視するキリスト教系の大学において、サービスラーニングが導入される事例が多かったようですが、近頃では日本のさまざまな大学において導入されています。
名古屋大学においても、現在のカリキュラムの中にすでに体験的な学習を含む学部や大学院は多数見られます。体験的な学習は、単に専門分野の知識やスキルを得るだけでなく、コミュニケーションの能力を高めたり、学生自身のキャリアを考えたりする機会にもなるため、カリキュラムにおける位置づけ、他の授業との関連、評価の方法などを考慮する必要があります。現在実施されている体験的な学習の質を高めるために、サービスラーニングという枠組みで捉え直してみてはいかがでしょうか。
(かわらばん2008年秋号, 中井俊樹)
少子化に伴い、各大学は志願者を確保するために入試科目を削減する傾向にあります。来たる平成21 年度国公立大学入試においても、推薦入試の実施割合は92.9%、いわゆるAO(アドミッションズ・オフィス)入試の実施割合は41.0%に上り、一貫して増加傾向にあります。センター入試を受けた後の二次試験(個別学力検査)においても、国立大学では2教科型が、公立大学では1教科型が主流となっています。こうした傾向は私立大学においても顕著です。入試科目の減少に伴い、志願者の学習履歴が不十分となり、入学後の基礎学力不足が深刻化しつつあります。このため、高校での履修内容の補習を行う大学が急増しています。たとえば、高等学校の理科では化学と比較して物理や生物の履修率が低いため、未履修者および中途履修者のために、多くの大学では入学前もしくは入学後に補習教育を実施しています。数学や英語の補習を実施する大学もあります。
近年では、補習教育からさらに発展して、高校での履修者と未履修者を区別せずに、大学入学者全員に対して一定の学習到達目標を設定し、専門基礎へと水路づけを行う「初習教育」の試みも始まっています。北海道大学の「基礎理科」では、カリフォルニア大学バークレー校の初習カリキュラムをモデルとし、物理学や生物学の初習教育を大規模授業の形で実現しています。この「基礎理科」には、大教室における演示実験や複数のTA による学習サポート、E ラーニングシステムの活用、演習問題や詳細な解説を含んだ教科書の活用など、学生の学習意欲を高めるためのさまざまな工夫が凝らされています。初習教育では文字通り「初めて習う」という前提に立って、プログラムを編成することが求められます。その際に鍵となるのは、到達すべき基準を設定し、学生に明示することと、初習者の学習意欲を刺激するような丁寧な教材づくりであると言われています。
(かわらばん2009年冬号, 近田政博)
地域住民や非政府組織が持ちこむ問題や要望に応えて、研究者が調査や開発を行い、その成果をサービスとして提供する。このような活動、またはその運営組織を、サイエンスショップと言います。1970年前後のオランダの学生運動において、大学所有のリソースを広く市民に開放しようとした試みをルーツとしており、近年では学術機関による社会貢献のひとつの形として注目されています。
ショップといっても商業性はなく、大学や市民団体による非営利の活動です。大学教職員と学生の協同運営や、学生の正課教育の一環としている事例もあります。また、サイエンスと銘打ってはいますが、自然科学や工学、医学などに限らず、人文学、社会科学も含まれています。
サイエンスショップは現在、ヨーロッパ、アジア、北米などで実施されています。米国ではルーツを異にするCommunity-basedResearch が1960 年代から続いており、近年はサイエンスショップの国際ネットワークと連携するようになりました。日本では、原子力資料情報室や科学と社会を考える土曜講座といった市民団体による活動が以前からありましたが、大学としての取り組みはごく最近になって熊本大学、大阪大学、神戸大学などで始まったところです。
サイエンスショップ成功の鍵は、クライアントの積極的な関与にあると言われます。問題の本質を明らかにする、解決へのプロセスをモニターする、提供されたサービスを評価する。さらに、実際に研究活動に加わったり、提供されたサービスを活用・維持するための訓練を受けたりもします。こういった訓練も、サイエンスショップが提供するサービスに含まれるのです。ここに、教育と研究を司る大学がサイエンスショップの主要アクターと目される所以があると言えるでしょう。
※本稿は「研究者のための科学コミュニケーションStarter's Kit」をもとに構成しました。
(かわらばん2009年春号, 齋藤芳子)
キャリア教育は、学生に将来の生活展望を持たせたり、進路の可能性の拡大・実現に必要な基礎的知識・スキルを習得させたりするための活動です。
日本の大学、とくに私立大学の多くは、従来から学生の就職支援に熱心に取り組んできました。これらの活動が学生の就職を後押ししてきたことは間違いありません。しかし、近年は、経済状況が複雑で景気変動の周期や幅も大きいうえに、学生の多様化が進んでいることもあり、卒業間近に行う支援活動だけでは就職を促進することが難しくなっています。そのため、多くの大学では、在学の全期間、さらには卒業後の生活など長期にわたるキャリア発達の促進・支援へと活動の幅を広げています。キャリア教育は、支援活動の中で中核的な位置を占めるものです。私立大学だけでなく、国立・公立大学でも普及しているのが近年の特徴です。
キャリア教育の具体的内容としては、職業意識形成に関わる授業科目やインターンシップが中心です。授業科目として開設する場合は、各学部・学科・専攻科・別科科目(必修・選択)としても実施されていますが、多くは全学共通科目の選択としての扱いです。インターンシップも8 割近くの大学が実施していますし、授業科目の中で実施する大学も全体の過半数に達しています(日本学生支援機構『大学等における学生生活支援の実態調査』(2006))。
長期の生活を展望しつつ卒業後の生活で活用できる知識・スキルを習得させようとするキャリア教育は、高等教育の本来の目的に沿うものです。そのために、ことさらに時間を設けて行わなくても、通常の教養教育や専門教育を通じて行うことが可能であり必要であるという指摘もあります。
(かわらばん2009年夏号, 夏目達也)
大人数の授業では資料を配付するのも、準備するのも一苦労です。そこで便利なのが、「コースパケット」を作っておくことです。コースパケットとは、授業(コース)を通して学生に配布する資料や情報をひとまとめにして開講時に配布するというものです。たとえば次のようなものが含まれます。
- 受講生に配布する詳細なシラバス
- 発展的な学習のための参考文献ガイド
- 予習のための教材(論文のコピー、新聞の切り抜きなど)
- 授業中に使用する教材
- 復習のための教材(練習問題、ヒント、解説、解答例など)
- 成績評価の対象となる課題資料
- 質問カードやコメント用紙
教員にとってコースパケットを作成・配布することのメリットは、毎週のように配付資料を準備したり、「先々週のプリントをください」と要求する学生への対応に追われたりする必要がなくなることです。学生にとっても、コース全体を通してどのくらいの課題があるのか、どれだけの学習量を求められるかを把握することができます。
コースパケットは小冊子にしたり、バインダーで綴じたり、さまざまな形態が考えられます。受講生が多い場合は生協の印刷部にまとめて発注したり、自作教材で未刊行の場合はダウンロード可能なファイルの形でウェブ上に載せて、受講生に自分で出力させたりすることもできます。
コースパケットを作成する際は配付資料の著作権に留意する必要があります。教育目的の場合に限り、他者の著作物を複製・配布することが特例的に認められています(著作権法第35 条)。この場合も出典を明記し、あらかじめ著者の了解を得ておくのが望ましいでしょう。配布対象は受講生に限定され、無料であることが条件です。教員によるこうした配慮は、著作権に対する受講生の意識を高めるきっかけにもなることでしょう。コースパケットには様々な可能性があるのです。
(かわらばん2009年秋号, 近田政博)
論文やレポートなどの学術的な文章を書くことをアカデミック・ライティングと呼びます。もともと日本で「アカデミック・ライティング」を冠する授業は、英語論文の書き方を教えるものでした。現在では、同じ「アカデミック・ライティング」という科目名ながら日本語論文の書き方を教える授業が開講されるようになっています。このなかには、留学生を対象にして日本語の論文作法、いわゆるアカデミック・ジャパニーズの習得をめざす授業もあります。他方、近年増加しているのが、初年次学生一般を対象とする授業です。アカデミック・ライティングはノート・テイキングやプレゼンテーションなどのスタディ・スキルズの一つとみなされ、このようなスキルを入学後の早い段階で習得させる必要性が広く大学関係者に認識されるようになったのです。
その背景には、アカデミック・ライティング教育の射程の広がりがあります。学術的な言葉遣いや文章の構成方法、引用の仕方、註や参考文献の書き方を教えるにとどまらず、思考力を育成することも課題となってきたのです。論文作成においては、当然のことながら思考力が求められます。とりわけ、仮説を立て、根拠に基づいた論拠を示し、結論を導くという論証の過程においては論理的に考えることが要求されます。他者の主張について妥当性を検討する際には複眼的に思考しなければなりません。思考力は大学において学習するにも社会に出て活躍するにも必要なものであり、その育成をアカデミック・ライティング教育は担いはじめたのです。
いっぽう2000 年頃からは学生のライティングを授業外で支援する動きが広がっています。早稲田大学をはじめ、学内にライティングセンターを設置する大学が増え、名古屋大学附属図書館のラーニング・コモンズのようにライティングを含む学習サポート環境も整えられつつあります。授業課題の添削指導の内容によっては成績評価を左右しかねないといった問題もあり、アカデミック・ライティングに関わる授業外での支援と授業との連携のあり方は昨今の議論の対象となっています。
(かわらばん2010年冬号, 久保田祐歌)
日本の大学ではあまり見られないファカルティ・ディベロップメントの形態として、教員メンター制度があります。大学において豊かな職務経験をもつ教員が新任教員のメンターとなり、新任教員が大学教員として成長していくことを支援する制度です。赴任間もない新任教員にとって、メンター教員との交流は、個別大学の文化を知り、そのコミュニティの成員となるための貴重な経験だと考えられています。
メンター制度は、新任教員にメンター教員を紹介して「後は2人でよろしく」というものではありません。教員メンター制度が有効なものとなるよう、多くの大学が活動のガイドラインを定めています。たとえば、初回のミーティングでは、メンター教員と新任教員の間で活動の進め方について合意書を作成することが求められます。メンター活動の目的、ミーティングの場所と頻度、相互の授業見学をするかどうか、活動の過程で得られた個人情報の取り扱い、活動の報告の方法などを相互で確認しながら決めていくのです。
ミーティングにおいて、メンター教員は、自大学の特徴、学生の特徴、参加できる研修機会、参考となる書籍などについて話すことが奨励されています。状況に応じて新任教員に紹介できるよう、図書館、学生サービス部門、教育支援部門、研究支援部門といった学内のさまざまな組織について理解しておくことも必要です。早い段階に2 人でキャンパスツアーを実施するという方法もあります。一方、メンター教員が自身の教育観や研究観を新任教員に押しつけることは、プライベートに立ち入ることと同様に、避けるべきであるとされています。
教員メンター制度は、新任教員のみでなくメンター教員にとっても意味があります。メンター教員は新任教員と意見交換することに意義を感じていること、また自らの教育研究を振り返り今後のキャリアを考えるきっかけとなることが調査で明らかになっています。
(かわらばん2010年春号, 中井俊樹)
欧米諸国では、文章作成を支援する場としてライティングセンター(以下、センター)を設けている大学が数多くあります。センターによる支援の動きは韓国やシンガポールなどにも拡大しており、それぞれの状況に応じた活動を行っています。ただし、各国のセンターに共通する特徴として、活動の目的を文章の修正ではなく、自立した書き手の育成としている点が挙げられます。
センターで来訪者に対応するのは、多くの場合、大学院生のチューターです。チューターは専門家や指導者としてではなく、一人の読み手として来訪者に接します。面談において様々な問いかけを行うことで来訪者の思考を促し、書き手自身が文章の修正の仕方や今後の方向性を見出していく支援をします。チューターはこうした活動以外にも、学期の開始時に研修を行ったり毎週ミーティングを行ったりしており、チューター自身の文章作成力も向上するといわれています。
アメリカのセンターの場合、学生のみではなく教員がセンターを訪れ面談を受けることも珍しくありません。センターは文章作成法の教育の場ではなく、読み手とのやり取りを通して書き手がより良い文章を書けるよう支援する場だからです。こうしたことの背景には、文章作成とは個人的な作業ではなく、他者からの指摘を受けて考え直し、書き直しを繰り返してより良い文章を練り上げていく協同的な作業だとする考え方があります。そのため、様々な立場の人がコメントを求めてセンターを活用しますし、図書館など利用しやすい場所にセンターが設置される場合が多く見られます。
日本の大学では、文章作成の方法に関する科目の設置は拡大しているものの、センターの設置はまだ多くありません。両者は異なったアプローチをとっていますが、目的に応じた設計が必要という点は共通しています。ライティングセンターの役割は、それぞれの大学によって異なってくるのです。
(かわらばん2010年夏号, 伊藤奈賀子)
教員養成における教育方法のひとつにマイクロティーチングという手法があります。マイクロティーチングとは、5 分から15 分程度の短い時間で、小グループの学習者役を対象に教師役が模擬指導を行い、その批評や評価を受けて改善に取り組むことで、教授法の技能を習得する方法です。
マイクロティーチングは、学習者間で教員役と学習者役を決めて実施するロールプレイング法のひとつの形態といえます。看護婦役と患者役を決めて行う看護技術実習、被告人、裁判長、弁護人などから構成される模擬裁判実習など、現在ではロールプレイング法はさまざまな分野で活用されるようになっています。マイクロティーチングは、1963 年にスタンフォード大学で開発された手法と言われています。当時は、5 分間の模擬授業、10 分間の評価と批評、15 分間の休憩、5 分間の再授業という構成でした。現在では、世界中の教員養成や現職教員研修において活用されています。また模擬指導の状況をビデオで録画し再生しながら改善点を検討するという方法も一般的になっています。
このマイクロティーチングという方法は、大学のFD 活動においても注目されています。ハーバード大学にあるデレック・ボック教授学習センターの教授法研修のひとつの柱は、マイクロティーチングです。6 名の教員が教師役と学生役を順番に担い模擬指導を行いながら、教授法の技能を向上していくという方法です。参加者が希望すれば教授学習センターのスタッフと共にビデオを視聴しながら議論することもできます。教授学習センターのホームページには、「マイクロティーチングは、短い時間で実施可能で、効果が実証され、かつ楽しい手法である」と記されています。
近年では、日本の大学のFD 活動においてもマイクロティーチングを活用している事例が増えてきています。名古屋大学においては、英語による授業のワークショップや大学院生対象の大学教員準備プログラムなどで活用されています。
(かわらばん2010年秋号, 中井俊樹)
職業資格や学位などの資格を授与する際に、過去の関連する学習の履歴や、学習を通じて獲得した知識・技能を一定程度評価する制度を学習歴認定制度といいます。資格の授与に限らず、教育機関における単位認定等に適用される場合もあります。
資格取得には、正規の教育機関で所定年数の教育を受け、その課程を修了することがしばしば条件とされています。これに対して、学習歴認定制度では多様な学習経験を通じて獲得した知識・技能を評価します。それが資格取得に必要な水準を満たしていると判断される場合に、資格を授与するのです。評価の対象となる学習歴は、フォーマルな教育だけでなく、インフォーマルな教育も認められる場合が少なくありません。
同制度の対象者は、通常の学校教育を受けている学生・生徒ではなく、社会人に限定される場合が一般的です。成人は、青少年と比較して提供される学習機会が少ないうえに、時間的・経済的な諸条件によってさらに学習機会が制限されるからです。とくに職業に従事している場合には制約が大きく、資格を取得して社会的条件を改善しようとしても実現は困難です。同制度には、成人に便宜を図ることにより、資格取得や生涯学習・継続教育に対する彼らの意欲を高める狙いがあります。
高等教育においては主に入学資格の認定に適用されていますが、国によっては学位授与審査に適用されています。この場合、所定年数の在学・学習や単位認定等の通常の手続きを経ずに(部分的に免除されて)学位を取得することが認められるのです。一部の学生のみに適用される制度であることから、平等性という観点からの問題が指摘されています。その一方、高等教育における学位授与や能力評価の伝統的なあり方に見直しを迫り、新たな課題を提起しているとみることもできます。
(かわらばん2011年冬号, 夏目達也)
学生が大学の授業に対して抱く不満の一つは、「高い教科書を買わされたのに、あまり使われなかった」というものです。大学に入るまで「教科の主たる教材」としての教科書を使い続けてきたためでしょうか、大学においても授業は教科書に沿って行われるものと思われてしまいがちなのです。
大学教育においても、概説書や入門書としての教科書が用意されている学問分野は多々あります。しかし実際の授業では、教科書の内容や配列から離れて独自の視点で組み立てなおしたり、要素の足し引きをして自前の配付資料を作ったりしている例が多く見受けられます。この場合に指定されている教科書とは、事前や事後の自主学習を支援する役割を担っていると考えられます。
一方、古典として位置づけられる基本文献を講読したり、複数の参考文献を組み合わせながら授業を進めたりすることも日常的に行われています。中世ヨーロッパに誕生した大学における教授学習は古典や聖書を徹底的に読み込む作業でしたから、むしろこちらが大学の教科書の本流というべきかもしれません。こうした諸文献も、大学では教科書と称されています。
大学の教科書が初等中等教育のそれと大きく違うところとしては、①政府による検定がなく、どのような書物を選ぶかが大学教員の裁量に任されていること、②そこに書かれていることが多様な解釈のなかのひとつに過ぎない場合があること、③学問分野の発展に応じて内容が書き換えられていくスピードが速いこと、などが挙げられます。それゆえに、大学教員にとって教科書を執筆することは、研究者としての資質を問われるものであり、かつ重要な使命のひとつといえるのです。
(かわらばん2011年春号, 西原志保+近田政博)
近年、欧米の大学では学士課程教育における学生の研究体験を促進する方策がとられています。「学生の研究体験」と聞くと、多くの方は卒業研究を思い浮かべるのではないかと思います。学生の研究体験の中に卒業研究を位置づけることはできますが、学生の研究体験はより広い概念です。米国において学生の研究体験を促進している学生研究体験協議会は、学生の研究体験を「学士課程学生によって実施され、専門分野に対して独自で知的もしくは創造的な貢献をする探究や調査」と定義しています。
学生の研究体験の形態は多様です。研究体験を初年次から段階的にカリキュラムに配置している大学もありますし、一部の優秀な学生を対象にカリキュラム外のサマープログラムとして提供している大学もあります。また、学士課程の学生が研究発表する場を設けたり、学士課程の学生を対象にした論文誌を発行したりする学会や大学もあります。
学生の研究体験は、1969 年に開始されたマサチューセッツ工科大学のプログラムが起源だと言われています。同プログラムは、教員の支援のもとで学士課程学生を研究プロジェクトに参加させる活動でした。これまで米国の研究大学における学士課程教育に対しては厳しい指摘がなされてきました。そのひとつは、「多数の学生が、同じ大学に所属する世界的に著名な研究者と会うこともなく、そして本格的な研究活動を体験せずに卒業してしまっている」というものです。学士課程の学生にとって研究とはいかなるものかという根本的な問いかけを含む指摘と言えます。
日本の大学と同様に最終学年次における卒業研究が重視されてきた英国の大学においても、研究体験のあり方が見直されています。英国の場合、学生が研究活動に主体的に参加しているという意識が低いことや、最終成果である卒業論文が本人と指導教員にしか読まれない場合が多いことが問題視されています。
卒業研究よりも広い学生の研究体験という概念は、学士課程教育の再構築に対して新たな視点をもたらすものだと言えるでしょう。
(かわらばん2011年夏号, 中井俊樹)
「コモンズ」とは共有地や入会(いりあい)を指す言葉です。そこから派生して、「ラーニング・コモンズ」とは「学習のための共有空間」(以下、LC)を意味します。名古屋大学でもLC が中央図書館の玄関を入ったところに2 年前に開設されました。日本の大学にも主として図書館内にこのようなスペースを設ける例が増えてきています。
LC はこれまでの図書館の概念を大きく変えつつあります。その最大の特徴は、文字どおり協同学習を促進する環境をつくりだしたことです。従来の図書館は静粛を保つべき空間でしたが、LC では日常会話レベルの話し声は差し支えありません。また、名古屋大学の場合には密閉できるドリンクならば持ち込むことを認められています(他のスペースでは不可)。長時間の活動に耐えうるように利用することが想定されているからです。
このことは、図書館が「本を借りる」「読む」という個人単位の機能に加えて、「仲間と一緒に調べる」「思案をめぐらす」「相談する」「協力して書く」という総合的・協同的な知的生産活動の拠点へと変貌しつつあることを物語っています。その効用は、所属する研究室の決まっていない学部学生にとってより大きいと考えられます。
一方、電子ジャーナルやデータベースが発達したことにより、教員や大学院生はそれぞれの研究室で必要な情報を検索・入手することができるようになりました。図書館から足が遠のいているのは、むしろ教員の方かもしれません。
学生がLC を最大限に活用するためには、教員側にもいろいろな工夫が必要だと思われます。たとえば、グループで課題に取り組むような授業を設計し、成績評価にもグループ活動での貢献度を考慮してはどうでしょうか。授業の前半はLC 内のセミナールームを使ってのレクチャー、後半はオープンスペースでグループワークという方法も考えられます。図書館のリソースを十分に活用せざるをえないような課題を学生に与えれば、LC の効果をいっそう高めることができそうです。
(かわらばん2011年秋号, 近田政博)
インフォーマル学習とは、組織的系統的に教育が編成されておらず、学習目標や期待される成果も設定されないなかで、学習者の視点からはほぼ無自覚になされるような学習のことです。多くは日々の職業経験や生活経験から個人が学習することを指します。
教育や学習は正規の教育機関以外の場所・形態で行われるものが多々あります。その代表的な場所は職場です。職務に従事するための前提となる知識・技能は、多くの場合、入職前の正規教育機関で形成されます。入職後は組織的・計画的な教育訓練が提供される場合もありますが、それらの機会は限られています。多くの場合、職務に従事する過程で個人が経験的に知識や技能を習得しています。知識・技能の内容は職務に直結するものばかりでなく、職場の慣習・規律等に関連するもの、人間関係に関連するものなど多様です。組織的・系統的なものではなく、多様で雑多なものになる可能性があります。とはいえ、知識・技能の内容や水準は職務を遂行する上では有効であり、しばしば不可欠なものです。正規教育機関での学習活動だけでは獲得できないものもありえます。
このような知識・技能を積極的に評価しようとする取組は近年注目され、活発化しています。OECD やEU 等でも政策提言としてまとめられており、関連する研究成果も発表されています。その背景には、職務遂行に有効な知識や技能へのニーズの高まりの中で、正規教育機関以外の学習の有効性や重要性が着目されていることがあります。また、職業資格をもたない人への救済の意味もあります。彼らは職業をはじめ各種の活動に従事する過程で一定の知識や技能を習得しているため、それを評価して資格取得を促すことが社会政策的観点からも重視されています。
ただし、インフォーマル学習による知識や技能の内容はしばしば雑多であるために評価が難しくなります。また、それが正規教育機関での学習と対等とみなせるかどうかは微妙な問題で、雇用主を含めた社会一般の理解を深めることが必要になります。さらに、インフォーマル学習は低コストで実施できるため、教育・訓練関係の予算縮減の圧力を招きかねない点にも留意が必要でしょう。
(かわらばん2012年冬号, 夏目達也)
大学生の学修活動については、学生が高い意識をもってどれだけ主体的に課題に取り組んだかが重視されます。学修時間のことを英語ではstudy loadといいます。この表現には、学修は労働と同様の「負荷」であり、学修成果は時間量(学修時間)で測定できるという意味が込められています。この点に関して、これまで中央教育審議会は「単位制度の実質化」という表現を用いてきました。さらに2012 年3 月に発表された「中教審まとめ」では、学士課程教育の質的転換を図るために学修時間を実質的に増やすことが不可欠だという踏み込んだ表現がなされています。
Benesse 教育研究開発センター(2012)によると、授業の予習復習や課題に費やす時間が週1 時間未満という学生は約半数にのぼります。本学においても、授業以外の勉強時間が1 日1 時間未満の割合は6 割近くに達しています(名古屋大学『第24 回学生生活状況調査報告書』、2010 年調査結果)。このように、日本の大学生の学修時間が短いのは周知の事実です。
しかし、われわれ大学側にも課題はあるといえます。大学設置基準では講義時間の2 倍分の時間量を自発的な学修に充てることを前提としています。ところが、日本の大学では適切な時間割の組み方について十分に説明を行っていないので、多くの新入生は高校時代と同様に、時間割いっぱいに授業を詰め込んでしまいがちです。予習復習をきちんと行うという前提に立つならば、たとえば1日に8 単位相当の4 コマを履修するのはとうてい現実的ではありません。授業時間以外に16 時間の予習復習が必要になるからです。このような時間割を大学側が許してきたのです。
望ましい履修形態とはどういうものか、授業時間内外にどのような学修が必要とされるのかについて、大学側はガイダンス等を通じて新入生にていねいに伝え、適切な時間割モデルを示す必要があるでしょう。
(かわらばん2012年夏号, 近田政博)
学習スタイルに関する理論の一つで、コルブ(D. Kolb)により提唱された理論が有名である。彼は学習を以下のように定義している。「学習とは経験の変換によって知識が形成される過程である」。個人の得た経験の中から学習の要素をとりだし、それをなんらかの知識へと展開することといえよう。
コルブによれば、経験学習には、主に以下のような特徴が含まれる。①学習は過程であり結果ではない、②学習は経験に基づき間断なく行われる過程である、③学習は社会に適応する過程で、相反するモードを融合することにより行われる。
社会人が獲得する知識の約7 割は経験に基づく、としばしば指摘される。その背景には、社会人固有の事情がある。彼らは、職場や家庭でまとまった教育を受けることは時間的・経済的に難しい。一時的に職場を離れて行う研修であるOff-JT は多くの企業で行われているが、実際にそれを受講できる人は限られている。その機会の得られない人は、自己啓発による学習か、諸教育機関の提供する学習を自費で利用することになる。それが難しい場合には、身近な資源を用いた学習スタイルを追求せざるを得ない。一方、社会人は職務遂行の過程で、日々多様な経験をしており、職務外では得にくい経験や事前に想定できない経験も多い。そのような場合でも、対応策を考え状況を打開することが求められる。しかも限られた時間内で、という条件付きである。
そのような経験の中から学ぶことは少なくない。むしろ、Off-JT で学ぶこと以上に多くの学習要素が含まれることもしばしばである。現実の対応を求められる分、そこでの学習には、真剣さと切実さが要求されるからである。
ただし、経験に内包される学習要素を知識として創造するためには、その要素を純化・高度化させることが必要である。そのためには、それなりの努力とステップが不可避である。その一つは省察(Reflective Observation)であり、自分が行った経験を多様な観点から批判的に考察することである。次に「概念化(Abstract Conceptualization)」であり、考察から得られた素朴な知見を、多くの場面でも活用できるようにより普遍的な内容に高めることである。さらに「試行(Active Experimentation)」であり、得た知識を新たに発生する状況の中で多様な角度から試してみることである。この試行を繰り返しつつ、内容を吟味し深化させることが、より普遍的で高度な内容の知識を生み出すことにつながる。
経験学習論は成人の学習スタイルとして論じられることが多いが、一般学生の学習にも当てはまる部分は少なくないと考えられる。
(かわらばん2012年秋号, 夏目達也)
2012年8月の中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」では、学士課程教育における学修成果の一つの測定方法としてルーブリックが取り上げられています。
ルーブリックとは、「学習目標との関係に求められる達成事項の質的な内容を文章表現したもの」(佐藤、2006)であり、学習の達成状況レベルを評価するときに使用される評価基準です。評価水準である「尺度」と、尺度を満たした場合の「特徴の記述」で構成されます。論述形式の試験、小論文、実技などのように客観テストが適さない場合に、ルーブリックによる評価が用いられます。
ルーブリックという用語は、もともと「赤色」という意味で、中世修道院で生活する修道僧がラテン語のテキストを書き写す際に、赤インクで見出しを付けたことからできた言葉です(濱名、2010)。次第に等級分けという意味に派生して、教育分野では 1980 年代に使用されるようになったようです。
ルーブリックを使用することで、評価作業の初めと終わりで基準がずれることなく、採点基準を一定に保つことができます。ルーブリックにはそれ以外にも効果があります。たとえば、あらかじめルーブリックを学生に示しておけば、学生にとってどのような成果を目指せばよいのかのガイドラインにもなります。また、複数の評価者による評価のばらつきをなくすことにも役立ちます。
ルーブリックは個々の課題や授業の単位で設定することができますが、それにとどまらず組織や機関の成果を評価する手段としても利用されています。ウェブ上で公開されている中央教育審議会答申の資料編では、課程についてのルーブリックとして関西国際大学の例、科目についてのルーブリックとして米国ポートランド州立大学の例が紹介されています。
(かわらばん2013年冬号, 中井俊樹)
アクティブ・ラーニングとは、学生の主体的・能動的な参加を重視した教授・学習方法や形態のことです。中教審答申(2012年8月)でその実施の必要性が強調されるなど、大学関係者の間で普及しつつあります。「能動的学修」などの訳語が用いられますが、しばしば「アクティブ・ラーニング」がそのまま用いられています。同答申では「ディスカッションやディベートを取り入れた双方向の講義、演習、実験、実習・実技等を中心とした授業」としています。このような学習・授業は、名称・形態・内容とも多様です。双方向型学習、学生参加型学習、自律的学習、さらには問題解決型学習、課題探求型学習、問題発見学習(その具体例としてPBL学習など)等も、この範疇に含むことができます。
「学習」とは,「経験によって新しい行動傾向を獲得したり、既有の行動パターンに熟達したり、あるいはそのような行動の変化を可能にするような内的過程を獲得したり組織化、再組織化したりすること」といわれます(『新教育学大事典』1990)。自らの思考・行動様式を変容させたり、学んだ知識を社会の多様な場面で有効に活用したりできるようになるためには、学習内容に対する深い理解を得るとともにそれを自己内面化することが前提となります。それには、学習者自身が主体性を発揮して学習活動に取り組むことが必要不可欠です。そのように考えれば、学習には能動的であることが本来的に要請されます。逆に、これらの発揮されない活動は、外形的な条件を満たしても実質的に学習とは言い難いと言えます。そのため、「能動的学修」という用語は、同義反復に陥る可能性もあります。
にもかかわらず、このことばが最近改めて用いられている背景には、大学教育では、教員による一方向的で知識注入型の講義が伝統的に主流であること、学生による主体的な取組を促進・支援する視点が依然として不十分であることへの反省ないし批判があります(近年は改善の取組も進んでいますが)。生涯にわたって学び続けることが重視される状況の中で、学習過程への学生の積極的参加を促すような教育のあり方が、強く求められています
(かわらばん2013年春号, 夏目達也)
エンロールメント・マネジメントとは、大学が学生募集から卒業までの間に一貫して行う修学支援のことです。エンロールメント・マネジメントは、データに基づいて大学の意思決定を支援するインスティチューショナル・リサーチの主要な活動と位置づけられます。
エンロールメント・マネジメントの具体的な内容は、入試広報、授業内容、中途退学防止、就職支援、奨学金制度など、広範囲に及びます。エンロールメント・マネジメントでは、学生の入学前から卒業後までの各種データが活用されます。学生の入試成績、入学前の大学に対する意識、在学中の成績、出席状況、相談履歴、授業評価、課外活動の状況、奨学金受給状況、進路、卒業後の満足度などです。これらのデータを分析し、学生に対する具体的な支援策を検討します。つまり、入試、教務、学生支援などのさまざまな学内部署と連携することが求められる活動と言えます。
エンロールメント・マネジメントの概念が提起されたのは、1970年代のアメリカのボストン・カレッジと言われています。当時、ボストン・カレッジは、志願者の減少、退学者の増大、社会的評価の下落により経営危機の状態にありました。そのような状況のなか、入試部長に着任した数理物理学者ジョン・マグワイアが、数理モデルに基づく分析や多変量解析を行い、募集活動と学生支援に関して総合的な戦略を打ち出しました。その後、エンロールメント・マネジメントの手法が、他の大学に広く普及しました。
エンロールメント・マネジメントは、安定的に学生を受け入れ、在籍させ、卒業させるという大学の基本的な運営に関わる概念です。中途退学率の高いアメリカにおいて、中途退学率を減少させて授業料収入を安定化させることも期待されて発展した概念と言えます。日本においても、山形大学や京都光華女子大学のようにエンロールメント・マネジメントという用語を取り入れて修学支援を実践する大学が増加しています。
(かわらばん2013年夏号, 中井俊樹)
東京大学が平成27年度末までに4学期制(クオーター制)を導入することを発表し、大学の学期制について注目が集まっています。名古屋大学は2学期制(セメスター制)をとっていますが、今後もこの制度を維持するのが適当でしょうか。
戦前の帝国大学では、学期制は各学部の判断に委ねられていました。大学全体で学期が統一され、日本の大多数の大学が2学期制を導入するようになったのは戦後になってからです。その根底には、1回90分の授業(2時間みなし)を15週にわたって実施し、これを2単位と数える単位制の考え方があります。ところが2013年3月末に大学設置基準第23条が改正され、授業期間を柔軟に設定することが可能となりました。大学は教育上の必要性に応じて、10週よりも短い学期、あるいは15週より長い学期を設定できるようになりました。
現行の2学期制にはいろいろな問題が存在します。第1に、振替休日の多い月曜日は授業回数を確保するのが至難です。第2に、一年で最も暑い7月から8月にかけて前期授業の仕上げや試験をしなければならず、学生・教員ともに体力的な負荷が大きくなります。また、後期授業の最後の時期は旧正月に重なることがたびたびあり、多くのアジア人留学生がやむなく帰省を断念しています。第3に、週1回の授業が学習効果や記憶の定着率という点で適切なのかという問題があります。
これに対し、4学期制における一学期分は約2ヶ月間に相当します。同じ授業を週に複数回実施することによって、学生に集中的な学修を促すことが期待できます。教員側も担当授業を特定の学期に集中させることによって、サバティカル(研究休暇)をとりやすくなるなどのメリットが考えられます。
しかし、上述した2学期制の問題点のうち最初の2点は、4学期制を導入しても基本的に変わりません。また、従来通りの週1回ペースの方が学修上望ましい科目もありうるでしょう。年間の試験回数が増えることによって事務局の負担が増加したり、非常勤講師の確保が困難になるといった可能性も否定できません。学期制の変更にあたっては、そのメリットとデメリットを慎重に検討する必要があるでしょう。
(かわらばん2013年秋号, 近田政博)
近年注目を集めている学習形態のひとつに、「反転授業」があります。従来、学生は教員による講義によって知識を伝授され、授業外では必要な知識の確認のための予習や伝授された知識を定着させるための復習を行うことで知識の定着を図る、というスタイルが一般的でした。反転授業において「反転」(flip)するのは、教室内・外で行う学習です。学生たちは、動画教材によって「教室外」で知識伝授型・説明型の講義を事前に受講します。「教室内」で行うのは、事前に受講してきた知識を習得・活用するための発展的な学習活動です。
反転授業は、通信技術、ICT技術の向上によって普及してきたeラーニングのなかでも、オンラインによる学習と対面式学習を組み合わせたブレンド型学習(Blended Learning)と呼ばれるものの一種です。反転授業によって効率的な学習効果を得るためには、オンライン教材が充実していること、カリキュラム全体におけるオンライン教材の位置づけや対面式授業で取り入れる学習活動や指導のあり方を明確にすることなどが求められます。ICT大規模公開オンライン講座(MOOC、Massive Open Online Course)、カリキュラム、アクティブ・ラーニング、学修時間など、近年の大学改革・教育改革にとって重要なトピックを、反転授業という学習形態に関わる問題として取り上げることができるでしょう。
反転授業という学習スタイルには、確かに新しさや可能性を感じます。反面、授業時間外での知識獲得を前提とした授業づくり、学修時間の確保がどこまで可能なのか、といった疑問も残ります。「反転授業」をさらに「反転」させる「反・反転授業」がスタンフォード大学の研究チームによって提案されるなど、反転授業に関して、あるいは学習形態の多様化、最適化について、これからも活発な議論が行われていきそうです。
(かわらばん2014年冬号, 東望歩)
『ハーバード白熱教室』として日本でも有名になったマイケル・サンデル教授は、発問の技法が優れています。1000人を超える学生が集まる大講堂の中で、「自分の兄弟が万引きしているのを見つけたら、あなたは警察に通報するだろうか?」「君は養子をもらうとき、その子に値段をつけられるかな?」などの発問をきっかけにして、主要な哲学者の思想と関連づけて議論を深めています。
教員が学生に対して教育的な意図を持って問う行為を、発問と言います。質問の一種と捉えることもできますが、発問と呼ばれるのには理由があります。たとえば、「星の重さはどのように測定することができるのでしょうか?」という問いかけについて考えてみましょう。この問いかけが学生から物理学の教員に対するものであれば、答えのわからない人がわかっている人に尋ねる質問です。一方、この問いかけが物理学の教員から学生に対するものであれば、答えのわかっている人が教育上の目的のために尋ねる発問になります。つまり、答えがわかっていても学習を促進する上で尋ねるため、質問ではなく発問と呼ばるのです。
教員が指導するときの言葉を、大きく説明、発問、指示の3 種類に分類することがあります。説明、発問、指示の3 つのバランスを変えるだけで、授業の印象は大きく変わります。これまで日本の大学の講義形式の授業においては、説明を中心とした授業が主に実施されてきました。しかし、学生の主体的な学習の重要性が叫ばれる現在では、授業において発問や指示を効果的に取り入れることが求められていると言えます。
発問は指示と組み合わせて使用することで学生はより主体的に考えるようになります。たとえば、「ある星と地球の間の距離はどのように測定することができるのでしょうか?」という発問に関連して、「あなたの考える方法をノートに書きましょう」や「考えられる方法を隣の学生と議論しましょう」などの指示を与えることができます。
(かわらばん2014年春号, 中井俊樹)
シンク・ペア・シェアは、さまざまな授業において簡単に実施できる協同学習の技法です。1981 年に刊行されたフランク・ライマン氏の書籍によって広く紹介されました。
シンク・ペア・シェアは、文字通り「シンク(考える)」、「ペア(2人組)」、「シェア(共有)」の順序で議論させる手法です。シンクの場面では、クラス全体に質問を投げかけ、学生が一人で考える時間を取ります。必要な時間は課題の内容によりますが、1分間以上与えた方がよいとの報告もあります。次のペアの場面では、学生に2人組をつくらせ、質問に対する答えについて議論させます。受講者数が奇数の場合は、3人組もつくります。シェアの場面では、ペアで議論したことをクラス全体に共有させます。教員が議論の内容を報告するように指示をするなどして全体での議論をリードします。
この技法が広く普及している理由は、クラス全体の議論への段階的な活動を適切に設定している点にあると言えます。まず一人で考える十分な時間を与えた上で、2人という話しやすい少人数で議論するため、クラス全体の議論に向けた有効なウォーミングアップになります。
シンク・ペア・シェアは基本的な型ですが、慣れてくれば自分なりにアレンジを加えることができます。たとえば、シンクの際にワークシートなどに書かせる作業を入れる、ペアの際に2人より多くの人数にするなど、自分の授業の中の学習目標に合わせて変更することができます。
協同学習に関する研究では、研究者によって見解が一致しているわけではありませんが、4、5人のメンバーからなるグループが推奨されることがあります。ただし、2人で学習するという形態も学習目標によっては効果的な方法です。メンバーがあまり慣れていない場合や使える時間が短い場合などは、特に2人での学びが有効であると言われています。
(かわらばん2014年夏号, 中井俊樹)
グループ試験は、授業の最終試験を行う際、個人で解答する試験の直後に全く同じ問題を学生同士で相談しながら解答する機会を設け、解答を2 回提出させる方法です。試験直後は学生が正解を知りたいという欲求が最も高まっている時であり、学生間での教え合いを通して深く学んでもらうための教授法です。「Cooperative Exams」「Two-Stage Exams」とも呼ばれます。
グループ試験は1990 年前後の米国で医学・農学・工学分野の教員によって試みられ、学生の理解度を高めると同時に学生が積極的に取り組む教授法として効果的であるとする研究報告が出されています。正誤問題、多肢選択問題、組み合わせ問題、穴埋め問題、計算問題、短文解答など、学生間の解答の差異が明確な試験の方が、お互いの解答を得るプロセスに焦点化した議論が起こりやすくなります。また、受講者数が200 名を超える授業においても実施できます。
評価の方法は、個人試験80%、グループ試験20%など、成績評価におけるウェイトを事前に決めておく方が、成績上位者と下位者の双方に対してグループ試験に参加する動機づけを高められます。あるいは、単に個人試験の得点よりもグループ試験の得点が高かった場合のみ、特別加点をする方法もあります。
グループの編成は、学生の自由に委ねる場合と教員が指定する場合の2 つに分かれます。学生の自由に委ねる場合は、個人試験終了後に教室外で解答し、答案をオンラインで提出させる方法があります。教員がグループ編成を指定する場合は、試験後の教室でグループ試験の時間を新たに設けることになります。グループを指定する場合は4 人前後がよく機能するようです。前者は時間の制約がないという長所がある一方、グループを編成できない学生が出る可能性があります。後者はグループの人数や属性を教員が決められるという長所がありますが、個人試験直後に教室や時間を確保できるかが問題になります。
人は「教える時に最も学ぶ」と言われます。教員は学生間の議論を誘発する試験問題となるよう、学生の学習をよく観察し、学生を理解し、つまずきそうな部分に焦点化して問題を作成します。
(かわらばん2014年秋号, 中島英博)
アイスブレイクとは、受講者の緊張をほぐすことを目的とした活動です。参加者の不安や緊張を氷にたとえ、硬い氷をこわす/溶かすという意味を持っています。
授業の一回目に不安を感じているのは、教員だけではありません。学生もどのような教員が来るのか、他の受講生はどのような人なのかなど非常に不安を感じています。このような不安を和らげ、学生に参加しやすい雰囲気をつくるうえで、アイスブレイクは効果的な手法です。
アイスブレイクには、いろいろな種類があります。これまでのあなたの授業に対する学生の反応から、実施するアイスブレイクを決めましょう。もし学生が緊張して毎回授業に望んでいるようならば、楽しさを強調した活動を行うとよいです。反対に、学生が怠けているようなことが多ければ、授業内容と関連させたアイスブレイクをするとよいです。
アイスブレイクの手法は、さまざまな書籍やWebサイトで紹介されています。たとえば、京都産業大学は、大学の授業場面で使うことのできるアイスブレイクを集め、『キャンパスで使える!アイスブレイク集』を公開しています。
アイスブレイクには、ゲーム性の高いものがありますが、教室内でゲームをすることに抵抗を感じる学生も多くいます。もしゲーム性の高いアイスブレイクを実施するならば、短いものにするか、うまく機能していない場合に途中でやめることのできるものにしておきましょう。また、何のためにやったのか分からないということが起きないように、アイスブレイクをやる場合は、目的をきちんと学生に提示することが重要です。
個人的な質問というのは、初対面の人には答えにくいものです。その可能性がある質問や活動を避けることが賢明です。また、さまざまな理由でどうしても参加しづらい人がいる場合があります。参加しない権利を保障し、強制的な参加にならないようにしましょう。
(かわらばん2015年冬号, 小林忠資)
教授会とは、教授を中心とする教員団による合議制の審議機関です。中世に誕生して以来、大学は大学外のさまざまな権力からの干渉や弾劾と対峙しながら大学の自治を確立してきました。自由に学問的活動が行われるためには、大学自らが管理運営することが不可欠と考えられてきたのです。教授会は大学の自治の重要な担い手と言えます。
学校教育法において大学に教授会を置くことが定められていますが、教授会をどこに置くのかは各大学の判断に委ねられています。全学の教員から構成される教授会をもつ大学も見られますが、多くの場合は学部や研究科ごとに教授会が置かれます。教授会の構成員は、用語に表れされているように当初は教授のみでした。戦後に助教授その他の職員を加えることができるようになり、1960年代末の大学紛争を契機に助教授以下の教員が教授会に参加する大学が増加しました。
最近では大学のガバナンス改革の中で教授会の役割が変わろうとしています。平成27年4月1日から改正された学校教育法が施行されます。「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」と書かれた従来の条文から、「教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする」という条文に変わりました。審議という用語には決定が含まれているようにも読めるため、新しい条文では決定する権限をもつのは学長であることが明示されています。また、重要な事項については、学生の入学、卒業、課程修了の認定、学位の授与など具体的に限定されました。
全学的な取組が個別の学部の反対によって進まないなど、教授会が大学の改革を阻害しているという意見がこれまでもありました。今回の法律改正は、大学運営における学長のリーダーシップの確立を目指したものと言えます。一方、学長が教授会から述べられた意見と異なる意思決定を実際に行うことは難しいという意見や教授会の役割の限定が大学の自治を危うくするのではないかという意見があります。
(かわらばん2015年春号, 中井俊樹)
チューニングは、学習内容やカリキュラムを大学間で比較可能にする取組です。正確には、「欧州教育制度のチューニング(TuningEducational Structures in Europe)」と呼ばれます。 もともと欧州の大学は、各国が独自の歴史と制度を有し、カリキュラムや卒業生の能力を国の枠を超えて比較することが困難でした。しかし、優秀な学生が米国へ流出する危機感や、欧州内を移動する労働力の質保証を進めるため、2000 年頃より欧州共通の学位制度や単位互換制度を確立する動きが始まります。その推進方策の1 つとして、専門分野ごとに卒業生の共通コンピテンスを示したものがチューニングです。
2000 年以降、経営学・化学・地球科学・教育学・ヨーロッパ学・歴史学・数学・看護学・物理学の9 分野のコンピテンス提示から始まり、2010 年以降は41 の領域で、学士・修士・博士が備えるべき共通のコンピテンスと学習成果が示されています。これらは、各学会の協力を得て策定されたものです。各大学は、自大学の制度や自国の歴史を尊重しながら、コンピテンスの獲得を可能とする学習内容やカリキュラムを設計します。
Tuning には調律・音合わせという意味があるように、カリキュラムを緩やかに調整する点が特色です。カリキュラムの標準化や画一化は、大学の自律性を損なうと考えており、目的ではありません。登山に例えるなら、同じ山頂を目指しながらもルートは画一化せず、どのようなルートで登るかは各大学の自律的な判断に委ねています。
日本学術会議が提示した分野別参照基準も、同様の考え方に基づいています。分野別参照基準は、専門分野ごとに全ての学生が身につけるべきコンピテンスを示したものです。各大学はコンピテンスを参照しながら、各大学の理念や状況を踏まえたカリキュラム編成を行い、質保証と質向上につながる教育に取り組みます。
グローバルな環境下での教育の質保証では、共通能力証明や学位の国際通用性が重視されるようになり、チューニングのような共通コンピテンスに基づくカリキュラム改善は、多くの大学に参考となる取組です。
(かわらばん2015年夏号, 中島英博)
学問に携わる者に求められる高潔さをアカデミック・インテグリティと言います。インテグリティ(integrity)ですので、高潔さは誠実さ、清廉性、完全性などと言い換えられることもあります。研究倫理よりも広範な概念であり、学問に携わる大学教員、研究者、学生のすべてに適応される用語です。学生のコピペ問題などと連動して、近年注目されています。アカデミック・インテグリティに関する行動規範を定めたり、ハンドブックを提供したりする大学があります。
学生の具体的な行動としては、盗用(剽窃)をしない、実験や調査のデータを捏造しない、レポートの丸写しをしない・させない、カンニングをしない・させない、といったものが挙げられます。各自の知性・能力を適切に披露することが基本です。「見て見ぬ振り」も アカデミック・インテグリティに反する行為です。
重要なことは、なぜこれらの行為をしてはいけないのかです。同じ単位や学位をもらうのに不公平があってはいけないという説明がありますが、もしも全員揃ってカンニングしたらと考えると行き詰まります。「勉強したくてきたのでしょう?」という問いへの答えも「したい人はすればいい」になりかねません。アカデミック・インテグリティは学位の質を担保するものであり、これによって大学も学生にも利益があるのだということを共通理解にする必要があります。また、社会的な意思によって「学問の自由」が保証された大学という学びの場が成立していることから、それにふさわしい社会的責任を果たし、今後の継承を確保するという意味合いが肝要です。
一方で、学生がひとりで何もかも解決しなくてはと思い込んで孤立することがないように、適切な指導や体制も求められます。例えば、友人との議論を通じて考えを深めることを遠慮しないようにシラバス等で予め推奨しておくなどです。とはいえ、明確な線引きやルール化は難しいのも事実です。まずは生き生きとした学問の共同体をつくることが、アカデミック・インテグリティにつながると考えられます。
(かわらばん2015年秋号, 齋藤芳子)
履修系統図とは、大学が開講する授業について、科目間や科目区分間の関係性や履修順序(配当年次)等を示した図表をさします。この図表には、「カリキュラム・マップ」「コース・ツリー」などが含まれます。
カリキュラム・マップは、学部等の組織単位で、学生が習得すべき知識・スキル・諸能力と、開講する授業科目との対応関係を示す表です。表の列(横軸)と行(縦軸)の一方に開講科目名を、もう一方に知識・スキル・諸能力の具体的内容を配置します。知識・スキル・諸能力は、組織が掲げる学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の示す内容となります。各科目を履修することにより習得できる知識・スキル等をチェックし、表中に示された知識・スキル等と合致する場合に○印をつけます。科目がとくに重視する知識・スキルと合致する場合には◎印で示します。
コース・ツリーとは、カリキュラム・マップで示した表を、図として示したものです。①学部で開講する全科目を目的・内容・レベル等に応じてグループ化、②それらが配置される学年・学科を示す、③科目群を履修した後にどの科目群を履修すべきかを示す、④科目群の履修を通じて習得できる知識・スキル等を示す、という内容です。
これらを作成することにより、学生は学修内容の順次性や科目間の関連性を一目で理解できます。教員は、学部全体で開講する科目間の関係が把握でき、自分の担当科目がコース全体の中で担う役割を理解・確認できます。また、組織は、カリキュラムが学位授与方針で掲げる知識・能力等の形成につながるかどうかをチェックし、より適切なカリキュラムを設計できます。
学生に習得させる知識・スキル等は、一般に学位授与方針で提示されます。その策定や対外的な公表はほぼすべての大学が行っていますが、大学全体で定める人材養成目的や学位授与の方針等とカリキュラムの整合性を考慮する大学は2013年現在約74%にとどまっています(文科省調べ)。ポリシーと実際の大学教育との整合性の検証・調整は、大学全体ではまだ課題になっています。
(かわらばん2016年冬号, 夏目達也)
学修の過程や成果を記録及び収集したものを、学修ポートフォリオと呼びます。たとえば、学修目標、学修計画表、チェックシート、課題達成のために収集した資料や遂行状況、レポート、成績単位取得表などが、収集の対象となります。学修ポートフォリオは、学生自身の自己省察を可能とすることにより、自律的な学修を深化させることを目的とします。また、従来の到達度評価では測定できない個人の能力を質的に評価する手法、教員や大学が組織としての教育の成果を評価するための情報源としても注目を集めています。
ポートフォリオは、元来、「紙ばさみ」を指す言葉です。画家や建築家が自分の成果をアピールするために用いていた作品集がポートフォリオと呼ばれていました。教育の世界では、標準テストでは図ることのできない幅広い学力を評価する手法として、1980年代後半以降のアメリカを中心に発展してきました。日本でも、近年、学修ポートフォリオを導入する大学が増加傾向にあります(平成23年147校→平成25年190校)。また動画データも含む幅広い学修成果を柔軟に蓄積するインフラとして、電子ポートフォリオの開発も盛んです。
学修ポートフォリオを効果的に用いるためには、授業やカリキュラムとの関連付けが重要です。たとえば、①学修目標と評価規準の確認、②学修過程・成果の記録と収集、③目標と規準に照らした学修成果の取捨選択、④学修の動機や成長の振り返り、⑤教員あるいは学生同士での到達点の共有と更なる目標の設定、といったプロセスが効果的とされます。実際には、カリキュラムや授業の目的に応じ、無理のない範囲で導入することが肝要ですが、いずれの実践形態を採るにしても、学修の振り返りと自己評価を促すことで、学生自身が自律的に学修を発展させていく能力(メタ認知能力)を育むことが、学修ポートフォリオ運用の要となります。
(かわらばん2016年春号, 丸山和昭)
パフォーマンス評価とは、「ある特定の文脈のもとで、さまざまな知識や技能を用いながら行われる、学習者自身の作品や実演(パフォーマンス)を直接に評価する方法」です(松下 2012)。パフォーマンス評価では、「現実的な状況で、さまざまな知識や技能を総合して使いこなすことを求めるような課題」であるパフォーマンス課題を用います。たとえば、自動車運転の路上試験はパフォーマンス課題に相当します。
大学教育では、医療職や教員を養成する分野で実技の評価として取り入れられてきました。また、多くの授業で行われているレポート、論文、口頭発表による評価もパフォーマンス評価に含まれます。パフォーマンス評価は、単に知識を獲得したか否かではなく、思考力・判断力・表現力をどの程度獲得できたかを評価する方法の1 つです。
一方で、評価の基準が個々の教員の主観にゆだねられやすいという問題も指摘されてきました。その解決方法の1つとして提案されたものが、ルーブリック(2013 年冬号の本欄を参照)を用いた評価です。複数の評価者の間で評価の一貫性を確保するための道具として、近年ルーブリックを用いた評価は多くの授業で取り入れられています。
評価の一貫性を確保するもう1 つの取り組みとして、パフォーマンス評価型の標準テストがあります。たとえば、医学教育や薬学教育の分野では臨床実習前の試験として、客観的臨床能力試験(OSCE)が行われています。受験者が、模擬患者に対する医療面接において、所定の時間内に出された課題に取り組む試験です。また、OECD は「高等教育における学習成果の評価(AHELO)」の取組として、経済学と工学の2 分野でテスト開発を行いました。日本でも複数の大学が工学分野で問題開発と試行試験に参加しました。パフォーマンス評価型の標準テストは、卒業時における質保証や学習成果の国際比較に活用でき、他の分野でも活用が望まれる評価方法です。
(かわらばん2016年夏号, 中島英博)
大学教員としての資質向上を企図した、長期有給休暇をサバティカル・リーブと言います。授業、入試、各種委員会などの業務を免除され、国内外での研究活動や書籍の執筆などに費やされます。一般に研究休暇と訳されますが、欧米では、教育ないしは管理運営の能力開発や、政府の科学顧問就任のような政治任用に充てることもあります。欧米では、研修休暇として企業等にも広く導入されている概念です。
語源はギリシャ語で7日間に1日の安息日を意味するsabatikos。このため、各大学における規定では7年間の勤務を経て1年を上限に申請可能とするのが基本形で、サバティカル・イヤーと呼ばれることもあります。
日本では、法人化前の国立大学には在外研修の制度があり、法人化後は、サバティカル・リーブとして制度化されました。私立大学については、慶應大学や早稲田大学に1960年代から類似の制度が存在していました。近年は国公私の別なくサバティカル・リーブの制度化が進展しているそうです。ただし、実際に取得できるか否かは、大学や部局の事情によりけりです。
米国の大学では、2年間の休暇を例外的に認めるとする規程を時折見かけます。前述の政治任用を念頭に置いたこの例外規定。これをさらに延長させたのが元・米国国務長官のキッシンジャーで、この超法規的措置をしてキッシンジャールールと呼ぶ、とも聞いたことがあります。いわゆるキッシンジャールールは、博士論文の上限ページ数を指しますが…これは余談ですね。なお、テニュア教員のみに権利を認める大学もあれば、逆にテニュアトラックにある(終身雇用への移行に向けた試用期間中の)教員のみに権利を認める大学も存在します。
大学の機能が多様化した現実に鑑みれば、大学教員の資質向上、社会や産業界における研究課題の発見、大学に対するニーズの発掘、学内外のネットワーキング等々の機会として大学が積極的に位置づけ、大学の活力源にしていくことに検討の価値がありそうです。
(かわらばん2016年秋号,齋藤 芳子)
一文要約は学習評価技法(Classroom Assessment Techniques)の1つで、学習内容の理解度を容易に把握できる技法です。専門分野を問わず多くの授業で活用できます。授業中に紹介した理論、概念、トピック、キーワードなどについて、学生に一文で要約するよう指示します。その際に、誰による、何のための、誰のための、いつ、どこで、どのように、なぜ(6W1H)の7つの要素をできるだけ多く文章に含めるように指示します。
教員が準備に要する時間は短いものの、学生から集めた文章の評価には少し時間を要します。学生が授業中に取り組む時間は3潤オ5分程度が目安です。毎回の授業終了前に1回実施するのが標準的ですが、15分ごとに1回実施する例もあります。
標準的な教員の準備は、(1)当該の授業または過去の授業の学習内容のうち、特に重要な概念やトピックを選択する、(2)選択したトピックについて、6W1Hに関する要素をリストアップする、(3)模範的な一文要約を作成してみる、の3段階です。学生への指示の仕方は「HIVウィルスは免疫システムにどう侵入しどのような影響をあたえるか」のような形でもよく、「水力発電とは」や「看護過程の5段階」のような形でも可能です。学生が慣れないうちは「A年代にBによって提唱されたCとDは似た概念だが、CはEとFに基づいた理論であるのに対し、DはGとHに基づいた理論である。」のような一文要約例を示し、キーワードを入れさせる方法もあります。
一文要約は記憶・再生型の用語確認ではなく、抽象度の高い概念や複雑な概念の理解を確認するための技法です。教員は、要約を指示するトピックが、適度な知識の構造化や論理展開を含み、6W1Hに関する情報を含むよう、適切にトピックを提示する必要があります。
一文要約は形成的評価の技法であり、学生の成果を成績評価に含めないようにしましょう。成果は教員が回収して次回の授業で優れた要約を紹介したり、多くの学生が誤解している点を指摘するなどのフィードバックを行います。授業の最後に感想や疑問点を書かせている教員は多いと思いますが、一文要約はそれと同じ方法で、比較的簡単に学生の理解度を高めることができます。
(かわらばん2017年冬号,中島 英博)
大学教育の質を示す指標として注目を集める概念の一つに、「学生エンゲージメント」があります。学習に対する学生の取組や姿勢を意味する言葉で、とくに、学生調査の文脈で注目されています。基本的な調査内容は、「学生が学業に投入する時間と努力」と、「学生が学業に時間と努力を投入するための大学側の取組」の2 つです。このうち、学生の学習時間や学習姿勢は、従来の学生調査にも含まれる項目です。これに対し、学生の学習実態を把握するだけでなく、そこに影響を与える教員側の働きかけや、大学側の取組も含めて明らかにしようとするところに、学生エンゲージメント調査の新しさがあります。
学生エンゲージメント調査の質問項目は、授業内外での学習時間や経験、教職員との交流機会、大学の学習支援サービスの利用など、学生の行動や態度に関するものが中心となります。調査は米国で始まり、現在ではオーストラリア、ニュージーランド、中国等にも広がりを見せています。日本でも、東京大学が実施した全国大学生調査をはじめ、学生エンゲージメントに注目した設問を含む調査が行われています。
これらの調査の結果として、しばしば強調されるのは、教員側の努力だけでは学習成果は向上しないという点です。重要なのは、学生が入学以前から有している学習習慣と、入学後の学生エンゲージメントを高める環境です。すなわち、学生と教職員の密な交流の機会や、学生が自分の学習の意義を理解し成長を実感する機会が、教員側の努力と噛み合うことで、学習成果の改善がはかられるとの知見です。
他方、従来の学生エンゲージメント調査は、学問分野別の違いや、個別の大学が置かれた社会環境の違いについて、十分な知見を蓄積していないとの指摘もあります。個別の機関、個別の学問分野の文脈に即した形で、学生の学業への意欲を高め、学習成果を向上させるための適切な大学・教員側の取組を明らかにしていくことが、学生エンゲージメント調査における引き続いての課題です。
(かわらばん2017年春号,丸山 和昭)
この数年、STEM教育に注目が集まっています。STEMとは科学・技術・工学・数学の英語の頭文字を合わせたものですが、STEM教育は単に専門分野の教育を指すのではなく、教科を統合して教えたり、科学や数学の中で技術・工学の要素を強調したりする教育のあり方を含意します。
嚆矢となったのは米国政府が初中高等教育から生涯教育に至るまでのSTEM教育推進を強力に打ち出したことでした。複雑になった社会において今後も米国がリーダーであり続けるためには問題解決力やエビデンスに基づいた分析力などが若者に必要であり、各分野を統合して教えることを求めています。数値目標として2020年までにSTEM分野の大学卒業生を100万人増加させる、高等学校までにSTEM教育経験のある若者を50%増加させるなどを掲げ、各種の施策が組まれています。
オバマ前大統領が2009年にSTEM教育を演説に取り上げて以降は諸外国がこの用語を使いだしており、日本もその1つです。それらの国々は以前から科学技術教育や科学技術人材育成をそれぞれに謳っていたことから、STEM教育という用語に飛びつく背景に現状の閉塞感や打開への期待が感じられます。例えば日本の高等教育では、様々な要素がSTEM教育の名のもとに語られます。文系のための理数教育も、文理融合の理数教育も、高校物理未履修(主に生命系)の理工系学生の教育も、工学教育・技術者教育も、という具合です。
様々な要素を1つの用語で括る必要性を挙げるとすれば「社会の中の科学技術」を指摘することができます。一市民として科学技術と適切に付き合えること、科学技術の専門家として社会への影響を見極めてよい製品・サービスを提供できること、そのための専門家と市民のコミュニケーションのあり方などがこの概念に包括されるからです。すでにある多様な授業実践をもとに、STEM教育の具体的な課題に取り組んでいく時期にきています。
(かわらばん2017年夏号,齋藤 芳子)
「ラーニングアナリティクス」(以下、LAと略す)は、情報技術を用いて学習データを収集、分析、フィードバックすることで、学習・教育を促進するための研究、あるいは実践を指す言葉です。例えば、eラーニング教材や電子教科書の利用状況の分析から、理解が難しいポイントを特定する等の取り組みが、ここでいうLAが指し示す内容です。
LAは、2010年頃より欧米で盛り上がりを見せている分野ですが、近年では日本の大学でも普及が始まっています。たとえば九州大学は、2016年に「ラーニングアナリティクスセンター」を設立しています。九州大学の事例では、デジタル教科書やeラーニングシステム等によって収集された3,000万件以上の学習ログデータが、研究や実践に活用されています。具体的には、学習ログデータから学生の予習復習状況を把握する取組や、授業中のデジタル教科書の利用状況から学生の理解度をリアルタイムで可視化する等の取組が行われています。また、過去の学習履歴から成績のよい学生の特徴を抽出することや、学生の興味に応じて教材を推薦することも、LAの一環として進められています。
LAは、教育における情報技術の活用と、それらを通じた学習データの蓄積とともに、現在進行形で発展を続けている領域です。特に、LAの今後の課題として指摘されているのは、情報技術と学習科学との接続です。具体的には学習支援や教育評価といった専門知識と、情報技術や統計処理の専門知識を結びつけること、それを担当する人材を育成することです。また、学習ログの活用に関わる、プライバシーと倫理に関する問題も重要です。匿名化等の技術開発とともに、社会的あるいは法的なガイドラインの開発と定着が求められます。これらの課題への対応も含め、LAに関する国内外の動向が、今後とも注目されます。
(かわらばん2017年秋号,丸山 和昭)
近年あちらこちらで耳にするようになった「オープンサイエンス」。直訳すれば「開かれた科学」ですが、その定義はやや曖昧になってきているようです。学術論文のオープンアクセスや学術的データの一般公開などから、オンライン上の科学討議、はたまた市民の手による科学研究、市民が支援している科学研究などまで、現状では文脈に応じて様々な意味に用いられています。
オープンサイエンスという語を創作したM. ニールセンは、イノベーションを起こす新たな様式としてこれを提唱しました。ITの発展を契機として、多様な人々が協働することによる新たな知の創造の様式が始まっているというのです。したがって、先に述べたようなオープンアクセスやデータ公開は、目的ではなく手段という位置付けです。また、いわゆる学術研究にこだわらず、広く知的活動を対象に捉えています。例えば、オンライン上で将棋の次の一手を検討するような事例が含まれています。
ニールセンが紹介したいくつかのオープンサイエンス事例には、際立った特徴がありました。当該分野の専門家が関与し、ファシリテーターの役割を果たしていたのです。議論を整理したり、提供された様々なアイディアにヒントを得て革新的アイディアに辿り着いたり。こういった活動は、分野に精通した専門家ならではのことと想像されます。成果の質を担保するという面から、専門家の必要性を説く向きもあります。ただしファシリテーターとなった専門家たちは、多くの人のアイディアと議論があってこその成果だったと述懐しているそうです。
大学教育に目を移すと、初年次教育などに取り入れられている研究体験の中には、オープンサイエンスに近いものがあります。いっぽう高年次の研究指導においては、学生が一人で考え抜くことや、様々な議論を俯瞰して統合発展させることに重きが置かれます。後者はむしろ、オープンサイエンスのファシリテーターを育成することにつながるものでしょう。大学にとってのオープンサイエンスは、教育と研究と社会貢献を架橋し、大学と大学教育の意義を先鋭化させていくものなのかもしれません。
(かわらばん2018年冬号,齋藤 芳子)
多職種連携教育は、医療福祉分野を中心に普及が進む取り組みです。これは2つ以上の専門職が、実践の質を向上するために互いに学び合うことを意味します。医療の高度化と細分化、健康問題の複雑化が進む中で、専門職スタッフの連携を確保することが、安全かつ質の高い実践を行う上で不可欠の課題であるとの認識が、多職種連携教育に注目が集まる背景にあります。
多職種連携教育の基本は、2つ以上の職種の現職者や学生に対し、相互交流の場を用意することです。教育方法としては、PBL(Problem Based Learning)、観察型学習、e-ラーニング、あるいは講義等、多様な手法が採用されています。たとえば、医学生、薬学生、看護学生等が混合した数名程度のチームを編成したうえで、実際の医療福祉現場での事例を検討し、最終的にチームの学習成果を発表するという取り組みがあります。
多職種連携教育の評価指標の開発も進んでいます。代表的な測定尺度に、RIPLS(Readiness for Interprofessional Learning Scale)があります。日本語版RIPLSに含まれる項目は、たとえば「他専攻との合同学習は、自己の(専門職の持つ)限界を理解するのに役立つだろう」といったものです。多職種連携教育の効果に関する報告も数多く蓄積されています。これらの報告を総合した研究では、モチベーションの向上や、他職種への理解の向上など、多職種連携教育が参加者に対してポジティブな影響を与えるとの結果が示されています。
多職種連携教育は、医療福祉分野に限った課題ではありません。たとえば初等中等教育の教員養成の文脈では、教職課程コアカリキュラムにおいて、学校内外の専門家等との連携の必要性を理解することが求められています。また大学でも、IR担当者、URA等の新たな専門職域が生まれるなか、多様な職種間での連携の必要性が高まっています。これら幅広い教育分野での課題に対応していくうえでも、医療福祉分野の多職種連携教育の実践や課題には、学ぶ事が多いのではないでしょうか。
(かわらばん2018年春号,丸山 和昭)
教育に携わるための訓練を受けた博士課程の学生に「院生講師(Graduate Student Instructors; 略称GSI)」(※)などの称号を与え、学内において単独で授業を受け持つことができる制度を有する大学があります。UCバークレイ、ミシガン大学、カルガリー大学など、北米に多く見られます。院生講師による授業に対する学生の評価が高いという報告もなされ、注目を集めつつあります。
博士課程の学生が教える経験を持つことは、”Homines dumdocent discunt(人は教えるうちに学ぶ)”という古くからの考え方に沿った学習の一環であると同時に、昨今のアカデミア内外における博士の活躍への期待に応えるものです。ただし、訓練を含めた制度化が進められた背景には、大学院生が授業を担当することについて、教育の質の担保が保護者の関心の的となりだしたという事情があったといいます。
院生講師となるための訓練は、当然ながらティーチングアシスタント(TA)になるためのそれよりも高度なものとなります。例えば、当該制度採用の代表的存在とされるUCバークレイでは、訓練に特化したセンターが運営するカンファレンスへの参加およびオンライン倫理教育の修了と、各部局が開講する教授法に関する授業で合格することの3つが求められます。訓練センターではさらに、具体的なトピックスでの教育ワークショップや、より高度な教育能力の認定プログラムを通じて、院生講師の実践とキャリア形成を支援しています。
院生講師の制度は、TA制度と同じく、大学院生の経済支援という側面も持ちます。リサーチアシスタント等の採用が少ない学問分野において、日本の大学院生が休学して他大学の非常勤講師を掛け持ちする現状からすれば、自校で在学しながら教育に携わることのできるこの制度は、大学と大学院生の双方にとって合理的であると言えるでしょう。
※ 院生講師の制度は、Graduate Teaching Fellows、Senior Tutor など様々に呼称されます。ただし、異なる内容の制度にこれらの名称を使用する事例もあります。その点、Graduate Student Instructors の呼称はこの制度を過不足なく示すものとみられます。
(かわらばん2018年夏号,齋藤 芳子)
専門職大学は、2017年5月の学校教育法改正により、新たに設置されるものです(発足は2019年4月)。大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的としています。あくまで従来の大学の枠内で設置されます。特徴は以下のような点です。
①専門性が求められる職業を担うための実践的・応用的能力の育成を前面に掲げていること、②長期の企業内実習等を卒業単位の概ね3分の1以上としたこと、③教育課程の編成、実施、教員の資質向上に関し当該職業の従事者・事業者の協力を求めること、④クラスサイズ(同時に授業を行う学生数)を原則40人以下としたこと、⑤実務家教員の積極的任用を要求していること(必要専任教員数の概ね4割以上)、⑥入学者について、職業に従事して実践的能力をすでに修得しており、専門職大学の教育課程の一部を履修したと認められる場合に、修業年限を最大半分まで短縮できること、です。
なかでも、産業界との連携が多面的に追求されている点は注目されます。産業界と連携した教育課程の編成・実施や実務家教員の登用等です。さらに、入学前に実務経験を通じて職業の実践的能力を修得している場合に、当該実践的能力の修得を授業科目履修とみなし単位認定できる仕組み(4年制で30単位まで)も注目されます。このような措置は欧米では珍しくありませんが、日本では従来みられなかったものです。高度職業人材の養成に加えて、社会人の受入れも主要機能として掲げていることの必然の結果とみることができます。従来の大学の枠組内でそれらの実施が追求されている点が重要です。
さらに、従来型大学も専門職学科を設置でき、それのみを設置する学部は「専門職学部」と称することも認められました。専門学校からの転換だけでなく、従来型大学からの転換も可能になり、相互間の移行が可能になりました。学術的知識の教授を伝統的に追求してきた大学に変化をもたらすことが期待されています。
(かわらばん2018年秋号,夏目 達也)
公的資金に基づいて行われた研究のデータのねつ造や論文盗用といった研究不正問題、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を契機とする科学者の責任問題、基礎研究を含めて両義性のある研究開発にどのように携わるべきかという、デュアルユース問題など、近年、科学と社会との接点において研究者の責任が問われる場面が見られます。このような文脈において、「責任ある研究・イノベーション(以下RRIと記す)」という考え方が注目されるようになりました。
RRIは、研究・イノベーションに対する社会からの期待を踏まえ、社会に及ぼす影響を予測・評価しながら行われる研究・イノベーション活動のことです。その特徴は、研究・イノベーションを正負両面から捉えることや、活動の早い段階から研究者のみならず多様なステークホルダーがそのプロセスに参画することだと言われています。
大学における取り組みの一つは、所属研究者のRRI支援です。ただし日本では 「多様なステークホルダーの参画」以前に、研究倫理や公正研究すらおぼつかない状況にあります。そのため、各大学では研究倫理に関する規程や綱領の制定、またそれに関連する内部組織の立ち上げなどが行われています。大学は、この研究倫理に関する課題を乗り越えることに加えて、社会により開かれた研究活動に向けた所属研究者のRRI支援を行なっていく必要があるでしょう。
大学におけるもう一つの取り組みがRRI教育です。ヨーロッパではHORIZON2020という科学技術政策のもと、「高等教育機関と責任ある研究イノベーション(HEIRRI)」プロジェクトが高等教育機関向けの教育プログラムを提供しています。機関レベルでは、オランダのライデン大学とデルフト工科大学、エラスムス大学ロッテルダムが共同して実施する「責任あるイノベーション」という学部生向けのプログラムが有名です。日本の研究・イノベーション活動において多様なステークホルダーの参画を進めるために、科学技術とは直接関わらない学部学生に対しても、共通教育等を通してRRI教育を行うことが大学には期待されていると言えるでしょう。
(かわらばん2019年冬号,東岡達也)
「大学教員が研究や教育に費やす時間はどのくらいか?」との問いに対して、直接的に答える公式統計がFTE調査です。大学教員や博士課程在籍者等を対象に標本を抽出した調査として、文部科学省が実施しています。最新の調査は2018年度に実施されました。大学教員の多忙化や、研究環境の劣化の問題とも関わり、政策決定の場でも取り上げられることの多い調査です。
FTE調査の元々の目的は、日本の研究活動の規模を、研究時間に即した形で他国と比較することにあります。比較のために算出されるのが、研究者数のフルタイム換算値です。例えば、1日当たり8時間勤務の教員の研究時間が4時間であった場合には、その教員を0.5人分のフルタイムの研究者としてカウントする、という考え方です。
FTE調査の特筆すべき点は、研究時間だけでなく、教育や社会サービス、その他の職務を含めた、職務活動時間の全体を把握するところにあります。このような特徴のもと、過年度調査からは、大学教員における研究時間の割合の低下傾向と、教育、社会サービスの時間の割合の増加が指摘されています。他方、FTE調査については、各年度の手法に違いがあるため、単純な経年比較は難しいとの指摘もあります(科学技術・学術政策研究所、2015)。自己申告に基づく調査のため、正確な職務時間が反映されていないという可能性も否定できません。
FTE調査には限界もありますが、大学教員の詳細な職務時間に関するデータは、他の公式統計には代えがたいものです。論文数や担当授業数といった指標には表れにくい業務負担の問題を、個人や個別の大学をこえた問題として検討するためには、FTE調査のような全国データが欠かせません。2013年の調査からは、研究パフォーマンスに影響を与える要因の把握にも焦点が当てられています。今年度に公表予定の最新の調査結果も含め、詳細な分析が待たれるところです。
(かわらばん2019年春号,丸山和昭)
単位制度とは、修得した単位数によって卒業や修了を認定する仕組みです。日本では、大学設置基準という省令のなかで、1単位は授業時間内外での45時間の学修内容を標準とすること、卒業要件は124単位以上であること、卒業研究等以外は試験をして単位を与えることなどが定められています。
単位あたり45時間という設定は米国に倣ったもので、週あたりの学習時間は124[単位]×45[時間/単位]÷4[年]÷2[学期/年]÷15[週/学期]=46.5[時間/週]となっています。法定労働時間より少し多いものの、少々の残業と一部を集中講義に置き換えることにより、妥当な時間数となります。ちなみに修士課程は、大学院設置基準により、30単位以上の単位修得および修士論文等への合格が修了要件です。つまり、時間の観点からは、学部の研究指導は単位に含め、2年間の修士課程の研究指導は単位外に設定すると整合性が高まります。
授業時間内と時間外の割合は、基準内で柔軟に設定できます。講義・演習は45時間中15潤オ30時間、実験・実習・実技は30潤オ45時間の授業を行えばよいのです。実験科目でいえば、授業後にレポート作成するのか、それとも授業時間内にレポート作成まで完了するのかによって、同じ授業時間数でも異なる単位数が設定できます。
お気づきのとおり、日本の多くの大学は、2時間ではなく90分間の講義を週1回15週にわたって実施して2単位としています。授業時間が60分単位で組まれることが多い欧州では、15分遅れで講義が始まる伝統(academic quarter、cum tempore)があり、実際の授業時間はあまり変わらないようです。
一方、日本では、単位の実質化、すなわち総学習時間の確保が強く求められる状況が続いています。このとき、週1コマ15週の講義に2単位という前例に縛られると、時間外学習の充実しか道がなくなります。しかし、講義30時間(実質90分×15週)と授業時間外学習を15時間で1単位とすることもできるのです。単位の早取りを嘆くならば、むしろ抑止力があるのは後者でしょう。突然のアクティブラーニング化に戸惑う学生にとって、授業時間内にチュートリアルを受けられるほうが安心できるかもしれません。
日本の大学において、時間外学習の充実がなかなか進まないという現状や、卒業論文を取り入れる大学が多いことを踏まえつつ、既存制度を活用して単位の実質化を図る余地は、まだ残されているようです。
(かわらばん2019年夏号,齋藤芳子)
奨学金は、学生の学業や生活を支え、教育の機会均等の実現を目指す経済的支援とその制度です。現在、日本の大学生の3割以上が何らかの奨学金を受給していることからも、奨学金の動向は注目されています。以下では「種類」と「対象学生の基準」という点から奨学金を紹介します。
奨学金の代表的な種類には次の三つが挙げられます。一つ目は返還義務のない給付型奨学金(grant/scholarship)であり、二つ目が返還義務のある貸与型奨学金(loan)です。後者には利息付きと利息なしの場合があります。三つ目はワークスタディ(work-study)です。これは対象の学生に一定の仕事を課す代わりに経済的援助を行う制度です。大学院生が行うTAやRAもこの制度に近く、アメリカでは優秀な大学院生を確保するために、授業料と生活費を賄うほどの金額が支給される場合もあります。日本の奨学金の大半は、日本学生支援機構による貸与型奨学金であり、さらにその約6割が利息付きです。日本は、OECD諸国の中で政府による給付型奨学金の比率が最も低いことが問題とされています。
対象学生の基準については、優れた学業成績を残した学生に奨学金を与えるメリットベース(merit-based)と、経済的に困難を抱える学生に対するニードベース(need-based)という二つの考え方があります。大学が独自に設置する奨学金は、優秀な学生の確保を目的とするためメリットベースになりがちです。教育の機会均等を目指すには、政府がニードベースの奨学金を提供することが望まれます。
2020年4月から、一部の世帯の学生を対象に、日本学生支援機構の給付型奨学金を拡充する制度が始まります。この新制度によって、奨学金が上記のような課題を克服できるのか、今後も注目していく必要があります。
(かわらばん2019年秋号,東岡達也)
実務家教員とは、「専任教員のうち、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員」です。舶来の言葉ではなく、定まった英訳はありません。各専門分野では、従前から実務経験をもつ教員が重要な役割を果してきたところですが、今日、改めて「実務家教員」の用語が注目される背景には、次のような政策動向があります。
実務家教員の役割が、特定分野をこえて制度上に明確に位置付けられたのは、専門職大学院の導入時(2003年)、及び専門職大学の導入時(2017年)です。これらの大学では、専任教員の概ね3潤オ4割を実務家教員で構成することが求められています。また来年度から実施される就学支援新制度(いわゆる無償化制度)においても、「実務経験のある教員等による授業科目が一定数以上配置されていること」が、大学側の要件になりました。さらに、今年の8月の大学設置基準の改正では、1年につき6単位以上の授業科目を担当する実務家教員には、教育課程の編成に責任を担うように求めることが明記されました。
実務家教員の数を示す正確な統計はありませんが、学校教員統計調査のデータが傍証として参考になります。企業等(民間企業、官公庁、自営業)から大学教員に採用される人数は、毎年1,500人から2,000人です。ただし、長期的な傾向を見ると、企業等から採用される大学教員の割合は、1995年をピークに逓減傾向にあります。このような状況下において、より積極的に実務家教員を大学において増やしていこう、活用していこうとの意志が、上記の政策の背景にあります。
直近では、文部科学省の実務家教員養成プログラム(持続的な産学共同人材育成システム構築事業)の拠点校として、3つの大学(東北大学、名古屋市立大学、社会情報大学院大学)が採択されました。これらのプログラムにおいては、質の高い実務家教員を養成し、各大学での採用へとつなげる仕組みの開発が期待されています。
(かわらばん2020年冬号,丸山和昭)
エクステンションとは、大学が有する知的・人的・物的資源を社会に開放する活動のことです。英米で始まったUniversity Extensionを起源とし、文脈によって「大学拡張」や「大学開放」と訳されますが、ここでは総称的に「エクステンション」の語を使用します。
エクステンションは、歴史的に「大学教育の開放」から始まりましたが、現在では「資源の開放」や学生の地域貢献活動もその内容に含むようになりました。「大学教育の開放」には、社会人入学者や科目等履修生の受け入れなどの「正課教育の開放」と、公開講座に代表される「正課以外の教育の開放」があります。また「資源の開放」は、学外の講演会・委員会等への教員の参加協力や、図書館等の学内施設の開放、産学連携活動などを含みます。近年では、大学の地域連携を促進する「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」や社会人の学び直しの機会を提供する「職業実践力育成プログラム(BP)」などの政策においてもエクステンションが推進されています。
大学がエクステンションを行う上で重要な役割を果たしているのが、生涯学習センター、エクステンションセンター等の学内専門組織です。2012年度に公表された「開かれた大学づくりに関する調査」によれば、「公開講座」に関する専門機関・組織を設置している大学は66.2%、「地域連携」は59.0%、「産学連携」は52.9%でした。5年後に行われた2017年度の調査では「公開講座」は69.6%ですが、「地域連携」は77.2%、「産学連携」は62.7%に増加しており、短期間でエクステンションが拡大していることが読み取れます。
一方、同調査では「大学の人手・人材の不足」や「地域との連携の意義が学内に浸透していない」、あるいは「予算が確保できない」ことなどが課題として指摘されています。また、国立大学では専門組織の改組・再編が進んでおり、限られた資源の中で拡大する多様な活動をどのように両立させ、運営していくかが課題となっています。
(かわらばん2020年春号,東岡達也)
私たちは学生の成績の差を、個人の知能の差が反映されたものと考えがちですが、知能よりも学習課題に投入した時間が重要という立場から異を唱えた米国の心理学者がキャロルです。学校学習の時間モデルでは、課題達成の度合い(学習率=成績)は、課題の達成に必要な時間に対して、実際にどれだけ学習に時間を使ったかの割合で表現できると考えます(市川尚・根本淳子(2016)『インストラクショナルデザインの道具箱101 』北大路書房)。すなわち、このモデルでは、必要な時間をかければ、誰でも課題を達成できると考える点がポイントです。
たとえば、Aさんは課題達成に1時間の学習が必要であり、実際に1時間学習すれば、学習率は100%になります。しかし、課題達成に必要な時間は個人差があり、2時間の学習が必要な学生が1時間しか学習しなければ、学習率は50%です。
学習率=学習に費やされた時間/学習に必要な時間=許容された学習時間・学習持続力/課題への適性・授業の質・授業理解力
学習に必要な時間を左右する要因には、課題への適性、授業の質、授業理解力があります。学生の既有知識をふまえない課題は、多くの学生にとって適性を欠く課題になります。そのため、課題の達成に必要な知識や技能は全て授業の中で身につけられるよう、授業の質向上が必要です。また、理解力をより高められるよう、多様なメディア・経験・方法を組み合わせた学習を用いて、理解を促す工夫が必要です。
学習に費やされる時間を左右する要因には、許容された学習時間と学習持続力があります。許容された学習時間は、ある課題を学ぶためにカリキュラムの中に用意されている学習時間です。学習持続力は所与の学習時間の中で実際に学ぼうと努力して使われた時間を指します。
急速にオンライン授業が普及する中、学習時間モデルは、学生に適した課題設定と、学習時間を増やす教材提供の重要性を教えてくれます。オンデマンド教材は、自分のペースで学習でき、繰り返し学習できる工夫をすることで、各自に必要な学習時間の確保を促すことができます。また、やさしい内容から難しい内容に配列する、クイズや小テストの頻度を増やし理解度確認を促す、内容と社会・生活問題との関連を示して意欲を高める等の工夫は、学習持続力を高めることにつながります。
(かわらばん2020年夏号,中島英博)
「学問の自由」とは、一般に、①何を研究するか、②何を発表するか、③何を教えるかについて、制限や介入を受けないという自由を指します。この自由があってこそ学問は発展し、ひいては社会がよりよい方向を目指せるという認識のもと、欧米を中心として世界の高等教育に浸透している理念です。とはいえ、現実には、国や社会からの要請と綱引きの状態にあります。
また、研究倫理や研究公正、研究者の社会的責任などの面から、制限を受けるところがあります。たとえば、倫理委員会で認められた研究計画でなければ実施できない、盗用は許されず引用の表記を行わなければいけないと各所で規定されている、学協会の綱領等において軍事目的の研究には関わらないことを掲げている、といったことです。
また、文化的・政治的背景によって、その意味する範囲は異なってくることがあります。独裁国家における大学人の「不自由」は、想像しやすいところでしょう。ちなみに日本では、日本国憲法第23条に「学問の自由は、これを保障する。」と明示されています。初等・中等教育においては最大限にこの自由を享受することはできない(すなわち、一定範囲は認められる)とする判例や、発表と社会運動との境界に関わる判例があります。
ドイツには、また別の、「学ぶ自由(Lernfreiheit)」という固有の伝統があるそうです。学生側にも学問の自由があるという概念です。新型コロナ感染症が世界中で流行する現在、どのように学ぶかについての自由が一定の制限を受ける事例が多くみられます。せめて、何を学ぶのか、誰から学ぶのか、そんな学生側の自由度を高めることができたらよいのにと考えさせられる概念です。
自由には責任が伴うものです。上記のような検討をすることは、教授することの自由と対にされるべき、教育する側の責任であるという見方もできます。「学問の自由」とそれに伴う責任とを同時に考察することは、この自由をより深く理解するのに欠かせないものと考えられます。
(かわらばん2020年秋号,齋藤芳子)
日本において、幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の教員になるためには教員免許状の取得が必要です。教員免許状取得に必要な単位を履修できる大学の教育課程を教職課程と言います。教職課程を設置する場合、大学は学科ごとに課程認定審査を受けて、文部科学省の認可を得なければなりません。文部科学省のホームページによれば、2019年4月1日時点で、606校の大学に教職課程が置かれています。7割を超える大学に教職課程が設置されていることを考慮すれば、教職課程は大学教育の重要な一つの役割と言えます。
教職課程で必要とされる科目群の内訳をみると、「教科及び教科の指導法に関する科目」・「教育の基礎的理解に関する科目」・「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」・「教育実践に関する科目」・「大学が独自に設定する科目」の5項目から構成されています。教員免許状取得希望者は、それぞれの項目で所定の単位を取らなければなりません。なお、小学校および中学校の教員免許状を取得する場合、7日間以上の「介護等体験」もあわせて行う必要があります。
近年の教職課程をめぐる議論をみると、教員養成の質保証をどう実現するのかが大きな課題となっています。実際に、全国すべての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力を示した「教職課程コアカリキュラム」が2017年に作成されました。さらに、教員免許状の取得に関して、教職課程の履修を課すだけではなく、医師・看護師・薬剤師・法律家などと同様に、国家試験を導入すべきだという意見も、自民党の教育再生実行本部などから挙げられています。教職課程を全国的に標準化しようとする動きの中で、教員養成にあたる各大学がいかに自主性および独自性を発揮するかも大きな課題となっています。
(かわらばん2021年冬号,藤井利紀)
機関別認証評価は、国公私立の全ての大学が7年以内に1回の受審が義務づけられている評価制度です。評価主体は文部科学大臣の認証を受けた評価機関であり、大学の機関別認証評価機関には、大学基準協会、大学改革支援・学位授与機構、日本高等教育評価機構など5機関があります。大学評価の方法には大きく自己点検評価、外部評価、第三者評価の3つの方法がありますが、機関別認証評価は第三者評価にあたります
大学評価は、大学を取り巻く環境変化と密接な関連があります。大学進学率の上昇と大学数の増加は、大学の質保証に関する社会からの関心を高めました。1991年の大学設置基準の大綱化の際、自己点検評価が努力義務化されると、1998年に自己点検評価と評価結果の公表が義務化され、大学が学外の評価者に依頼して行う外部評価が努力義務化されました。その後、2003年の学校教育法改正により、大学と独立した第三者機関によって行われる評価である機関別認証評価が導入されました。自己点検評価や外部評価では、大学が評価項目を定めますが、第三者評価では評価項目や評価方法を第三者機関が決める点が特徴です。
2004年から始まった機関別認証評価は、2004年から2010年の1巡目、2011年から2017年の2巡目を経て、現在2018年からの3巡目に入っています。1巡目では広範な大学の活動を評価していましたが、2巡目では教育面以外の活動の評価を簡素化するとともに教育の内部質保証の観点が追加され、3巡目では内部質保証に重点を置いた評価項目となっています。認証評価制度の趣旨は、大学が恒常的に自己点検と改善を進め、その集大成として7年に一度受審するという自律性の尊重でした。しかし、認証評価の受審年にのみ自己点検を行うような事例や、点検結果をふまえた改善が十分でない事例が問題視されたこと等を背景に、内部質保証による継続的な点検と評価の取り組みが重視されるようになりました。
教育活動の成果や質は現場の教職員が最もよく知っているものですが、現場の経験を文書で表す労力は膨大です。効率性を重視すると、評価担当教職員を中心に学生調査や規程類の整備など認証評価基準をクリアできる資料を整えて受審することが合理的になってしまいます。できるだけ現場の経験を反映できる根拠資料の収集方法を開発することが、今後の課題といえます。
(かわらばん2021年春号,中島英博)
プレFDは、大学教員を志す大学院生、ポスドクを対象とした大学教員への準備プログラムです。1993年にアメリカで始まり、日本では1999年に広島大学で試行されたのを先駆けに、2005年から京都大学において「大学院生のための教育実践講座」、名古屋大学において「大学教員準備講座」がスタートしました。これら二つは、全学向けプログラムですが、京都大学「文学研究科プレFDプロジェクト」、広島大学「教職課程担当教員養成プログラム」、北海道大学「高等理学教授法」などのように、学問分野別のプレFDも行われています。なお、プレFDについては、「かわらばん」第69号も参照できます。
文部科学省が実施した調査「大学における教育内容等の改革状況について」(2019年度)によると、38大学がプレFDを実施しています。38大学は、博士課程を設置している大学の約8%に過ぎないことと、プレFD実施大学数が横ばい状態にあることを踏まえると、プレFDが十分に普及していないことが分かります。2019年8月の大学設置基準の一部改正によって、各大学院が博士後期課程の学生に向けてプレFDの実施または情報提供をすることが努力義務となりました。このことをきっかけに、プレFDに対する大学院側の向き合い方が変わる可能性があります。しかし、大学院生側に目を向ければ、彼らの多くがプレFDに参加しているわけではありません。多くの大学院生にプレFDに参加してもらうために、プレFDを参加者にとってより魅力やインセンティブがあるものに変えていくことなどの努力が必要となるでしょう。さらに、多くの場合、プレFDは学内向けプログラムとして実施されています。そのため、プレFDを実施していない大学の大学院生に対して、どのようにプレFDの機会を提供していくのかも課題となっています。
プレFDは内容面でも課題を抱えています。大学院設置基準において、プレFDは「学識を教授するために必要な能力を培うための機会」と定義されており、その目的は授業能力向上に置かれています。例えば、大学教員の採用審査では、書類選考および面接に加えて、多くの場合模擬授業を課されることからも分かるように、大学教員に授業能力が求められます。しかし、大学教員の職務は、研究や授業だけではなく、研究指導、学生支援、学内組織の運営、社会貢献などと多岐にわたります。こうした大学教員の多様な役割を踏まえれば、プレFDを単なる授業能力向上の場に限定するのではなく、研究、教育、大学運営、社会貢献を包括した大学教員にとって必要な基礎的知識と技能を身に付けることができる機会として捉え直す必要があるでしょう。
(かわらばん2021年秋号,藤井利紀)
マイクロクレデンシャルとは、学位取得を目指す学習よりも細かく区切られた学習単位と定義されています。詳細な定義は各国・地域で異なり、名称についてもバッジやナノディグリー(ナノ学位)、サーティフィケイト、ライセンス等があります。ニュージーランドでは2018年に制度化されており、資格よりも少ない単位の学習量で、技能の発展に焦点を当てたもので、かつ従来の高等教育では提供されていない学習と規定されています。オーストラリアでは、バッジを集めることによって学位取得が可能な大学もあります。欧州高等教育圏における調査では25カ国でマイクロクレデンシャルが設置または開発されていますが、高等教育機関が提供または承認するものに限定されており、必要な学習量、成果測定の方法と観点等が定められ、欧州基準による質保証が行われています。
日本では、2007年に学校教育法の改正により、大学が履修証明プログラムを提供できるようになりました。これが日本におけるマイクロクレデンシャルの一例と考えられます。履修証明プログラムは、学位課程より短期間のプログラムを学生以外の者に提供することを目的としていました。現在では、社会人の学び直しの手段として浸透してきています。2021年度の省令改正により、大学院が実施する履修証明プログラムについて、当該大学院が大学院教育に相当する水準と認める場合に限り、単位授与を可能となる見込みです。職業キャリア形成に生かすことを目的に、産業界や職能団体などと連携した履修証明プログラムも検討されています。他大学や、産業界、職能団体などと連携した履修証明プログラムを発行するためには、共通の基準や質保証の設計に注意が必要です。このためには、国家学位資格枠組み(National Qualification Framework : NQF)の検討やeポートフォリオを用いた学習歴証明書のデジタル化などを検討しなければなりません。学習歴証明書のデジタル化は、国内外での就職活動、世界各地・全国各地で活躍する卒業生の海外赴任・転職活動のためにも必要と考えられて世界42カ国以上で実施されており、日本においても早期の実現が望まれています。
(かわらばん2022年冬号,北栄輔)
大学が自ら教育目標や到達目標を定め、目標に対する達成状況を質的、量的に測定することを通じて、教育改善を行う一連のサイクルのことを教育の内部質保証といいます。近年、教育の内部質保証の中でも、教育課程やプログラムを通じた学生の学修成果(Learning Outcomes)の到達度の評価(Assessment:アセスメント)が求められるようになりました。「学生が何を学び何を身につけたか」を示す学生の学修成果は、教育ポリシーにおいてはディプロマポリシーの「求める人材像」や「期待する能力・スキル」に記述されています。
教育の内部質保証の取り組みでは、一貫した教育目標に沿った、体系的な教育プログラムが構成されていることを社会に示していく必要があります。その出発点は大学のミッションに基づき設定された教育ポリシーや学修成果の到達目標です。この大学全体のポリシーや目標が、教育課程やカリキュラムの目標に、さらには個々の授業の学習到達目標へと繋がっており、成績評価や授業の内容にも一致していることが求められます。
一方でアセスメントについては、『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)』(2018年)でも、個々の授業や科目レベル、カリキュラムやプログラムレベル、学部・研究科や機関レベル、という階層毎にそれぞれのアセスメントサイクルを実施する必要があると言及されていました。もちろん、階層によってアセスメントの主体者や、組織体制、学修成果の到達度を検証するために用いるデータの種類等も異なってきます。
いずれにしても、大学全体から授業にいたるまでの教育目標の一貫性や学修成果の到達度をデータ等のエビデンスに基づいて検証し、改善をするという一連のプロセスの中で、学生の学びに大学がどのように貢献しているのか、またそもそも大学における学生の学びとは何かを、教職員や学生で対話を重ね、ふりかえる機会として捉えていくことが望ましいのではないでしょうか。
(かわらばん2022年春号,安部有紀子)
リカレント教育とは、学習と労働などの諸活動が交互に行われるべく提供される教育や、そのような教育制度をさします。1969年と1973年に、OECD(経済協力開発機構)がリカレント教育を報告書で取り上げたことをきっかけに、欧州から世界へと広まりました。その背景には、社会に出るまでの学校教育が長すぎることに対する疑問や、若者の高学歴化によって生じた世代間教育格差、急速に変化する労働環境と柔軟性の低い学校教育とのミスマッチといった、さまざまな課題への対応が求められていたことがあります。
当初の欧州におけるリカレント教育の特徴として、フルタイムの学習とフルタイムの労働を交互に行うよう設計されていた点があげられます。これは、終身雇用ではない欧州ならではの特徴でしたが、1980年代以降の世界的な経済不況やそれにともなう雇用の悪化を受けて、リカレント教育はパートタイムの学習ないし就労を含むものとなりました。また、職業訓練に特化した教育への変容も見られています。
現在、日本で注目されているリカレント教育は、いくつかの点で提唱された当時の発想と異なっています。1つは、終身雇用がいまだ主流であることを受けて、フルタイムで就労しつつパートタイムで学習するという形式が中心となっていることです。「社会人の学び直し」という用語にもこうした事情が反映されています。過去の日本は企業内教育が充実していて、リカレント教育の必要性があまりなかったという背景もあります。もう1つは、リカレント教育の実施主体として大学が主翼を担っていることです。欧州のリカレント教育は大学などのフォーマル教育に限らず、インフォーマルな教育も想定されていました。2022年「我が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について(第一次提言)」では、大学の本業としてのリカレント教育の位置付けを明確にすることがリカレント教育の推進方策の1つに掲げられています。ちなみに2020年度に行われた調査結果によると日本の大学等における学内組織の26.4%がリカレント教育プログラムを提供しているところであり、ここから更なる拡充が期待されている状況にあります。
ところで、リカレント教育は、その考え方が急進的であることが指摘されていました。なぜなら、リカレント教育の実現は教育制度の改善にとどまらず、雇用形態や労働条件の改善等の社会制度全体の変革を必要としていたためです。実は、日本におけるリカレント教育は、1990年代にも提唱されており、とくに職業人を対象とした大学院等の高等教育機関で実施されるものは「リフレッシュ教育」と呼ばれていました。しかし、高等教育機関や企業を巻き込んだ社会変革までには至らず、「補助金の切れ目が事業の切れ目」として、そのまま立ち消えとなるケースが多かったと言われています。そのため、現在のリカレント教育が「大学の本業」として位置付けられるためには、政策による推進はもちろんのこと、企業や高等教育機関自身が変化するような制度改革が必要とされるでしょう。
(かわらばん2022年夏号,東岡達也)
大学設置基準は、学校教育法第3条に基づいて、大学における教員数や施設、教育課程編成に関する最低基準を定めた文部科学省令です。文部科学大臣による大学や学部・学科等の設置認可に際しては、この基準にそって審査されます。また、認証評価においても、この基準の履行状況が確認されます。ほかの高等教育機関・課程についても、短期大学設置基準、大学通信教育設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、高等専門学校設置基準があります。
新制大学が発足してからの大学設置認可においては、任意団体である大学基準協会が定めた「大学基準」が審査に援用されていました。公的で明快な基準の必要性から1956(昭和31)年に公布されたのが大学設置基準です。翌年に施行されたのち、時宜にそって幾度もの改正がなされてきました。
たとえば、1960年代後半の学生運動を受けて一般教育の改善機運が高まり、1971年からは各大学の教育方針に基づいて一般教育課程をより弾力的に編成できるように改正されました。1991年には、高等教育の拡大や社会ニーズの変化、さらに新自由主義の台頭という背景をもって、いわゆる「大学設置基準の大綱化」と呼ばれる大改正がありました。この改正によって、学部名称の縛りがなくなり、新名称が次々と生まれることになりました。また、一般教育科目、外国語科目、保健体育科目および専門教育科目の区分も、この区分ごとの卒業に必要な単位数の設定もなくなり、教育課程編成の自由度が増しました。これにより多くの大学で教養部を廃止するという大変革につながりました。その後の改正のなかにも、教員名称と役割の変更(2006年)、講座・学科目制の規定削除(同)、FD義務化(2008年)、SD義務化(2016年)など、大学組織や大学教育の全般に関わるようなものが含まれています。
2022年10月の最新の改正では、教員配置を柔軟にする基幹教員制度、先導的な教育課程編成のための特例制度をはじめ、社会にひらかれた質保証や教職協働の再構築など、多くの要素が盛り込まれています。今般の改正は大綱化以来の大改正とみなされており、経過措置も数年にわたります。各大学において関連規程を改正し、その運用に留意すべきことはもちろんですが、よりよい大学・大学教育に結びつけていく実践にこそ注力できるようにしたいものです。
(かわらばん2022年秋号,齋藤芳子)
「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について(審議まとめ)」において、「客観性の確保」、「透明性の向上」、「先導性・先進性の確保(柔軟性の向上)」及び「厳格性の担保」の観点を踏まえた大学設置基準等の改正が提言されたことから、「大学設置基準等の一部を改正する省令」(令和4年文部科学省令第34号。以下「改正省令」という。)において、教育研究実施組織、基幹教員、校地、校舎等の施設及び設備、教育課程等に係る特例制度等に関する所要の規程の整備が行われました(大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布について(通知)、令和4年度9月30日)。この中から「基幹教員制度」を取り上げたいと思います。なお、「基幹教員制度」の英語表記については、現段階で定訳がないため、当センターによる暫定の訳を冒頭に記しています。
これまで運用されていた専任教員制度では、「一の大学に限り、専任教員となる」「もっぱら当該大学における教育研究に従事する」と定められており、専任教員の登用については、各大学で適切に運用していました。専任教員制度を基幹教員制度に改めることで、同一の教員を複数の大学/学部で学位プログラムに責任を持つ教員として算入することが可能となりました(学部のみ)。これによって、教員が不足しがちな分野について同一教員を複数大学/学部で登用したり、実務家教員を採用したりすることで、学位プログラムの教育の質を担保することを目的としています。
基幹教員は3種類に分かれています。いずれも教育課程の編成などに責任を担うことは同じです。第1は主要授業科目を担当する教員、第2は年間8単位以上の授業科目を担当する教員(もっぱら当該大学の教育研究に従事する者)、第3は年間8単位以上の授業科目を担当する教員(もっぱら当該大学の教育研究に従事する者以外の者)となります。第1の教員は、これまでの専任教員にほぼあたります。第2の教員は学内他部局を本務先とする教員、第3の教員は他大学や企業からの教員となります。ただし、第2、第3の教員の数は、大学/学部で必要となる最低教員数の4分の1までとすることとされています。ただし、1大学において、第1と第2の基幹教員を兼ねることはできません。第1と第3、第2と第2、第3と第3のような組み合わせが可能となっています。
(かわらばん2023年冬号,北栄輔)