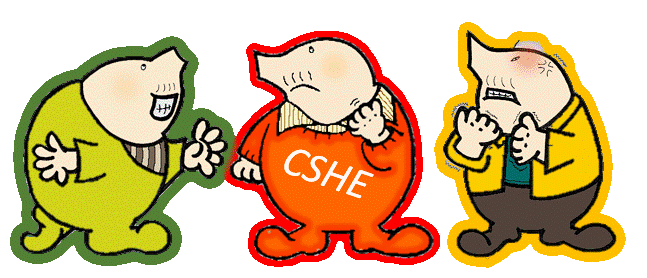2021年度名古屋大学学生論文コンテスト
学問のススメ、論文へススメ。
学生生活にスパイスは足りていますか?
授業に出る、レポートを書く、試験勉強をする、
サークルに入る、友達と遊ぶ、本を読む、アルバイトをする・・・
まだまだもの足りない人へ
学問の香りのスパイスを贈ります
――さあ、論文へススメ!

 2021年度審査結果
2021年度審査結果
2021年度名古屋大学学生論文コンテストの審査会を、2022年2月2日(水)に開催しました。藤巻朗理事・副総長、戸田山和久教養教育院長、佐久間淳一附属図書館長、北栄輔高等教育研究センター長による厳正な審査の結果、次の論文が選出されました。
受賞論文は、本学の研究成果物として名古屋大学学術機関リポジトリに登録されます。
 優秀賞
優秀賞
- 喧嘩両成敗といじめ自殺
- 法学部 福島 聡華さん
 優秀賞
優秀賞
- 丸物百貨店の盛衰に関する一考察
- 情報学部 津田 航さん
 優秀賞
優秀賞
- 居住形態と主観的・客観的困窮が大学生活の悩みに及ぼす影響
- 法学部 平松 莉奈さん
 佳作
佳作
- 理想の異性像と性役割観の関係性
- 文学部 佐野 彩葉さん
 佳作
佳作
- 現在の大学生は就職氷河期世代の大学生からどう変化したのか
- 文学部 高見 玲菜さん
 佳作
佳作
- 大学生の留学に対するとらえ方の差は何か
- 経済学部 杉本 稜晟さん
 受賞コメント
受賞コメント
【福島聡華さん】優秀賞
この度は優秀賞を頂きまして誠に有難うございます。私はアニメや演劇の影響で中世に興味を持ち、またゼミの延長線上で現代の人間関係について学んでいました。どれほど学問の細分化が進もうと、我々学生が常にそれに付き従う必要はなく、分野を横断することでしか見えない世界もあるでしょう。効率化が求められ、単位や進路とは無関係な勉強をすると眉を顰められる昨今、もしも拙稿がそれらに対するアンチテーゼとしての役割を果たすことが出来るとすれば、私としては至上の喜びです。
【津田 航さん】優秀賞
今回は、優秀賞という評価をいただき、ありがとうございます。
私は家族で百貨店へ行く機会が多く、なかでも京都駅北側に所在した近鉄百貨店京都店・通称「プラッツ近鉄」がかなり印象に残っています。京都出身の父や祖母が「マルブツ」と呼ぶことが不思議でしたが、のちに、この店を運営していた「丸物」という百貨店が全国展開していたと知ったのがきっかけでいろいろ調べるようになりました。京都で過ごした高校生時代、文化祭で発表してほしいという同級生の依頼を引き受けたものの、ネット上の不正確な情報に基づく発表で終わったことを後悔しています。
今回は「日経テレコン」、丸物の後身企業「京都近鉄百貨店」の社長を取り上げた書籍「新風 ある百貨店の挑戦」などを活用して、論文執筆に合わせた方法、かつスムーズな情報収集を心掛けました。かつて存在した店の詳細、父の記憶を裏付ける記述なども発見できたものの、さらなる情報のために何時間もかけて京都市の図書館へ通うなど、想定のようにはいきませんでした。論文の執筆自体も体裁がなかなか整わず、募集要項に合わせた形式を満たすのに苦労しました。
また、歴史を踏まえたうえで、「京都近鉄百貨店」が出店した、滋賀県の近鉄百貨店草津店(旧・草津近鉄百貨店)で現在行われている取り組み「タウンセンター化」について触れ、「丸物」各店と対比することで、今後の地方百貨店のあり方を考察しています。特産品の販売、専門店の導入と「丸物」や近鉄百貨店京都店と一見似たアプローチを行いつつも、外来者ではなく地元客への訴え、外部テナントではなく百貨の店員による高い接客など違ったやり方を取り入れ、集客につながっていることに注目しました。
今後、丸物ほか百貨店などの経営研究をさらに行いたい気持ちもあるものの、「タウンセンター化」のように地域密着型の取り組みを行うビジネスの実践にも気持ちが傾いています。研究だけではなく、実践しないと見えてこないメリットや課題もあると感じたからです。
最後に、執筆のきっかけを作ってくれた父と、このような研究について発表を行う機会を与えていただいた名古屋大学高等教育センター及び教養教育院の方々に厚く御礼申し上げます。
【平松莉奈さん】優秀賞
このたびは拙稿に優秀賞をいただき誠にありがとうございます。
大学入学後に一人暮らしをしている学生と話した際に「一人暮らしは大変だ」という人もいれば「一人暮らしは楽しい」という人もいたことから一人暮らしの実態や自宅生と自宅外生の違いに関心をもったことがテーマ設定のきっかけでした。特に最初はわからないことばかりでしたが、興味をもったことを論文にまとめ、さらにこのような賞をいただくことができ、大変嬉しく思っております。慣れない作業ということもありデータ分析には時間がかかってしまいました。しかし、この作業を通して、最終的には論文で取り上げなかったデータも含め、大学生活における自宅生と自宅外生の様々な違いを知ることができました。そのなかには自分の予想と異なる結果になったものもあり、大変面白く感じました。
この経験やいただいたフィードバックを今後にいかしていきたいと思います。データ分析や論文執筆で大変お世話になった基礎セミナーの先生方、授業内で様々な助言をくださった基礎セミナーの受講生の皆様、このコンテストを開催し、貴重な機会を与えてくださった名古屋大学高等教育研究センター及び教養教育院の皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。
【佐野彩葉さん】佳作
この度は、このような賞をいただき、誠にありがとうございます。本格的な論文を書くことは初めてで不安もありましたが、このように評価していただき、大変嬉しく思います。
本論文では、大学生の持つ理想の異性像と性役割観について調べました。私自身、将来は働きたい気持ちが強いです。同時に、結婚をして家庭を築くことへの憧れもあり、仕事と家族の両立を実現したいと考えています。しかし、実情を見ると、今もなお女性の家事負担が大きく、一体何が原因なのだろうかと関心を持ちました。本調査を通じて、改めて性別役割分業に関する問題の根強さに気づくことができ、今後も改善に努める必要があると感じました。
最後になりましたが、基礎セミナーの先生方や受講生、調査対象者の方など、たくさんの方々に協力していただき、この論文を書き上げることができました。本当にありがとうございました。
【高見玲菜さん】佳作
この度はこのような賞に選んでいただき、ありがとうございます。大変嬉しく思います。私は大学に入学して、家族や親戚などから聞いていた大学生活より自分の大学生活の方がよほど忙しいのではないかと感じました。そこで大学生の性質の変化というものに目をつけて、今回の論文を書くに至りました。
基礎セミナーの授業内では先生、TA、同じ受講生から多くの助言をいただくことができ、論文について一から教わりながら進めていく、非常に貴重な機会だったと思います。また、自分の興味のあることについて研究するということは初めての経験で、恵まれた環境であったことにとても感謝しています。いただいたフィードバックをもとに今後もより良い研究をし、論文を作成するということを目指していきたいと思います。この度はありがとうございました。
【杉本稜晟さん】佳作
この度はこのような賞をいただき、誠にありがとうございます。初めての論文作成だったため最初は右も左も分からず不安ばかりでしたが、先生方からのご指導や受講生との意見交換と言った協力を受けて、書き上げることができました。
私は今回、大学生がどのように留学を捉えているのか、また捉え方の差にはどのような背景があるのかについて研究を行いました。私自身を含め、留学に興味を持ちながらも自分の今後のことなどを考えてしまい、中々一歩を踏み出せない人が意外と多くいると感じたことがこの研究の動機となっています。
今回の論文作成にあたって、先行研究や調査、分析の方法など様々なスキルを学ぶことができました。この経験は今後の取り組みにも活かしていきたいと思います。この度はありがとうございました。
 事務局から
事務局から
本年度は、応募13作品のいずれもよく練り上げられた論文で、事務局としては嬉しい限りでした。このうちから、厳正な審査により、優秀賞3作品、佳作3作品が選ばれました。
福島聡華さん(優秀賞)は、喧嘩両成敗という日本的概念の歴史をふまえ、いじめ自殺に影響を与えていることを記述しました。明快な主張、丁寧な概念整理、緻密な論理展開、豊富な先行文献の活用など、論文全般が高く評価されました。
津田航さん(優秀賞)は、地方百貨店の戦後史研究を、その存続という現代的な問題と結びつけて論じました。テーマや分析の着眼点にオリジナリティがあること、企業史、新聞、雑誌等も用いて多くの事実を整理したこと、スムーズな論理展開などが評価されました。
平松莉奈さん(優秀賞)は、主観的困窮と客観的困窮という軸をもって自宅生と自宅外生の悩みの違いを描きだしました。膨大な二次データを丁寧に読み解き、説得力をもって記述したことが評価されました。
佐野彩葉さん(佳作)は、大学生の性役割観について、独自のアンケートにより仔細に検討しました。先行研究を踏まえた新たな視点での問題設定、仮説に基づいた緻密で挑戦的なアンケート設計、丁寧かつ明確な考察、なめらかで一貫した論文展開など、全般に高く評価されました。
高見玲菜さん(佳作)は、大学生の肯定感の上昇が、大学教育改革の結果ではなく、社会的・経済的な環境の向上にあると指摘しました。本学のデータと全国のデータに基づいた丁寧な検証を行い、先行研究と異なる結果を導いたことが評価されました。
杉本稜晟さん(佳作)は、大学生の留学に対する意識について仮説を生成し、独自の調査から丁寧な検証を行いました。論文構成、明快な説明、一貫した主張、実証パートの記述方法、考察の深め方などが、全般に評価されました。
選にもれた作品も、論文として一定のレベルに達していたことは記録として残したいと思います。独自のアンケート調査やインタビュー調査を行ったものが多かったなか、このコンテスト史上初となるオートエスノグラフィーに挑んだ作品もありました。いずれも、主張に沿って適切な研究手法を選び、丁寧に分析考察した痕が読みとれる、良作と評価されました。
次年度も、学生論文コンテストを開催いたします(応募要項などの一部が変更になる見込みですので、詳細がリリースされるまでしばらくお待ちください)。皆様の意欲作を楽しみにしています。

2021年度の募集は締切りました。ご応募ありがとうございました。
 応募要項
応募要項
 論文内容
論文内容
応募論文においてとりあげるテーマ/問いを明確に記述したうえで、文献等を活用して論じてください。内容領域は問いませんが、当該領域を専門としない人にも理解できるよう記述してください。(論文題目例がホームページに記載されていますので、参照してください。)
 応募期間
応募期間
2022年1月19日(水)正午まで
 応募資格
応募資格
名古屋大学に在学する学部1・2年生
 応募規定
応募規定
- 応募論文は、単著、未発表かつ日本語で書いたものに限ります
- 審査対象論文は1人1編のみとします
- 次項「応募方法」に掲載されている書式に従って、論文と応募用紙それぞれの電子ファイル(PDFまたはWord)を作成・提出してください
 応募方法
応募方法
-
論文本編と応募用紙の書式電子ファイル(PDFまたはWord)を当ページからダウンロードしてください
- 書式に従って論文と応募用紙を作成してください
-
論文本編と応募用紙の電子ファイル(PDFまたはWord)を、件名「2021論文コンテスト応募(応募者名)」で、応募先メールアドレスへ期日内に送信して下さい
- 応募先E-mail: info@cshe.nagoya-u.ac.jp
 応募先
応募先
- 応募先E-mail: info@cshe.nagoya-u.ac.jp
 応募先
応募先E-mail: info@cshe.nagoya-u.ac.jp
 審査
審査
本学教員による
 表彰
表彰
数名に賞状および協賛機関からの副賞を授与
 結果発表
結果発表
- 2022年2月を予定
- 発表に際し、入賞者の所属学科および氏名を公表いたします
- 入賞作品は名古屋大学学術機関リポジトリに掲載いたします
 その他
その他
- 論文作成のポイントしては次の資料(PDF)を参考にしてください。
- 論文の書き方に関する各種文献を中央図書館2階ラーニングコモンズおよび高等教育研究センター(東山キャンパス文系総合館5階)にて閲覧できます
- 中央図書館2階サポートデスクでは、大学院生スタッフからレポートの書き方の相談を受けられます
- 過去の入賞論文は名古屋大学学術機関リポジトリに掲載されています
- 過去の受賞論文タイトル・テーマについては、以下のリンクから確認できます
 主催
主催
名古屋大学 高等教育研究センター・教養教育院
 共催
共催
名古屋大学 附属図書館
 協賛
協賛
コクヨマーケティング株式会社
名古屋大学消費生活協同組合
 問い合せ先
問い合せ先
名古屋大学高等教育研究センター 2021年度名古屋大学学生論文コンテスト事務局
- Tel:
- 052-789-5696
- E-mail:
- info@cshe.nagoya-u.ac.jp
- URL:
- https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/ronbun/