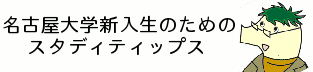
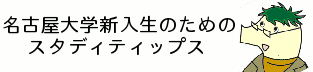
|
|
2.本から学ぶ 2.2 読書人になろう
せっかく本を買っても読む習慣がついていないと、途中でくじけてしまい、本棚の肥やしになってしまいます。新入生のうちに、日常生活の中で本を読む習慣をつけましょう。ここでは、どうやって読書の習慣をつけたらよいかについて紹介します。
本を読む習慣をつけるために、本を入れるのに十分な大きさの通学カバンを用意して、買った本をカバンに入れておきましょう。ハンドバックのような小さなカバンだけだと、本やノートは十分に入りません。そうなると、教科書やノートは大学の個人ロッカーに置きっぱなしということになってしまいます。何はともあれ、本をカバンに入れて携帯することが基本なのです。本を携帯することによって、電車の中や喫茶店でも活字に触れることができます。まずは、「どこでも読める」環境をつくるところから始めましょう。
あなたはいつもどの時間帯、どの場所で本を読みますか。自分にとってのお約束の読書パターンを作ってみませんか。たとえば、夜寝るときに30分でも枕元で本を開いてみてはどうでしょうか。読書をするということは一人になる時間をつくるということです。授業のみならず、人間の生活の大部分、たとえばアルバイトやサークル活動、携帯電話など、ほとんどの活動は他者との関係によって成り立っていますが、本を読むためには意識的に一人の時間をつくることが重要なのです。
大学生として本を読むということは、書いてある内容を正しいこととしてそのまま暗記するのではなく、それを自分なりにどう受け止めるか、「考えながら読む」ということです。つまり、あなたなりに評価をするということです。たとえば、「この本は世間で話題になっているわりには、内容はたいしたことない」「誰も注目していない本だが、○○の理由で僕は高く評価する」など。「考えながら読む」トレーニングをするには、本を読んだ後に感想・コメント・メモを書いてみるとよいでしょう。読書日記としてインターネットのブログを活用するのもいいでしょう。
本を一人で読む自信がなければ、友人と読書会をつくってみましょう。同じ本に興味をもちそうな仲間を募り、一緒に読む本を選んでみましょう。一人で読むのはくじけてしまいそうな本であっても、仲間と一緒だといいプレッシャーになって、最後まで読み通すことができるものです。また、友人のコメントから思わぬ知的刺激を得られるかもしれません。そのことが自分の視野を拡げるきっかけにもなります。
読書にも一定の約束事があります。自分が購入した本なら構いませんが、借りた本に書き込みをしたり、折り曲げたりするのはルール違反です。次に使う人が迷惑します。どうしても書き込みたいときはコピーを取りましょう。ただし、著作権法により一人につき一部、しかも一部分だけのコピーしか認められていませんので、注意してください。著作権とは人類の知的成果に対して敬意を払うことでもあります。CDやDVD、コンピュータのソフトウェアのコピーが禁じられているのも同じ理由です。 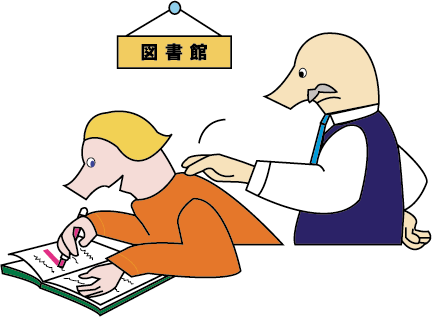
また当たり前のことですが、借りた本は返却日までに返しましょう。誰でも借りるときは必要に迫られていますが、返すときはついついルーズになりがちです。図書館の本は公共財(みんなの財産)であり、お互いの良心に基づいて運営されています。
【先輩からのアドバイス】
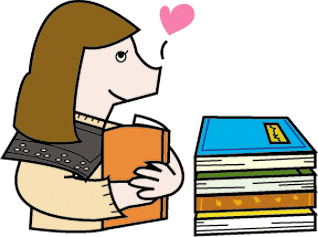 |
戻る |