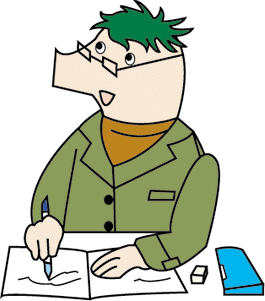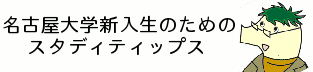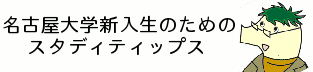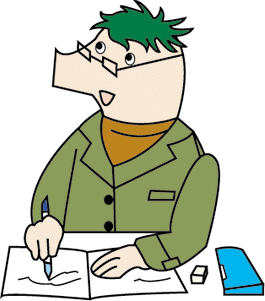ようこそ名古屋大学へ。名大はさまざまな分野で第一級の教授陣を数多く擁している世界レベルの研究大学です。あなたは、これらの教授陣を水先案内人として、学問・科学技術の世界に足を踏み入れようとしています。また、名大は膨大な蔵書・学術雑誌・データベース・実験設備を完備しています。これらをぜひあなたの学習に活用して下さい。
本号の姉妹編『名古屋大学新入生のためのスタディティップス(1)−「学識ある市民」をめざして』で紹介したように、大学は人類の知的遺産を保存・継承すると同時に、「新しい知」を発見・生み出す空間でもあります。そうした新しい知が創造される過程やその現場に立ち会う感動を、授業を通して教員から垣間見ることができます。大学の授業は最高水準の知を継承し、そして生まれたばかりの新しい知に触れるところです。これって、すごいことだと思いませんか。これからどうやって大学での学習を充実させていったらよいか、これから具体的なアイデアを紹介していきます。
|
ティップス1 大学は「知の共同体」であることを知ろう
|
大学の授業は高校までの授業といろいろな点で違いがあります。第一に、高校までの授業は、学習指導要領に沿って教える内容が決められていましたが、大学の授業では、何をどのように教えるのかは、教授陣がすべて自由に決めることができます。いかなる政治的・宗教的・経済的な理由をもってしても、大学の教育・研究活動に圧力をかけることはできません。これを「学問の自由」(アカデミック・フリーダム)といいます。
第二に、高校までは教員=教える人、生徒=学ぶ人、という立場の違いがありましたが、大学では学生も教員(学者)も、ともに「学ぶ」存在です。大学の授業のスタンスは、「学問のおもしろさをともに分かち合おう」「ともに学ぼう」というものです。大学は学びたいという気持ちを共有する空間、いわゆる「知の共同体」なのです。教員はあなたに対して、何かを強制することはありません。あなたが学ぼうとすることをサポートしてくれる存在です。
第三に、大学で学ぶ内容は、正解が一つとは限りません。正解はいくつも存在するかもしれないし、ひょっとしたら存在しないかもしれない。高校までのように、一つの解答が必ず存在するとは限りません。舗装された道路を決められたとおりに歩くのが高校までの学習だとしたら、大学の学習はコンパス(教員、教科書など)を片手に道なき道を自分で手探りしながら進むようなものなのです。それが大学での学習・研究の醍醐味でもあります。
まずは大学の授業に期待してください。高校までの授業と大きく異なるので、最初は戸惑うかもしれませんが、学ぶことの楽しさをだんだん感じることができるでしょう。
|
ティップス2 つまらないからといって価値のない授業だと決めつけない
|
大学の授業の価値は一つの尺度では測れません。今はその授業の価値が理解できなくても、あとになってから実感するということも十分にあります。若いときには理解できなくても、歳月を重ねてから気づくことはたくさんあります。全学教育は全人的な教養を磨くところですが、ともすると若いあなたには抽象的で役に立たない話だと感じられるかもしれません。一方、数学や物理などの基礎科目は記号と数式ばかりで、いったい何の役に立つのかと疑問に思うかもしれません。
しかし、つまらないからといって、内容がわからないからといって、価値のない授業だとレッテルを貼らないようにしてください。つまらないと感じるのは、ひょっとしたら、あなたにまだその授業を受け止めるだけの力が備わっていないからかもしれません。その授業で学んだ基礎概念がのちのち必要になるかもしれません。そういうことは実際によくあります。「今はわからなくても、いずれわかるようになりたい」という気持ちを持って、しばらく辛抱して取り組んでみてください。
【先輩からのアドバイス】
- 自分から行動をおこせ!大学は良くも悪くも自由。高校までは方針を与えられ、その道筋に沿ってこなせばよかったのに対し、大学では黙っていても周囲の人が自分を助けてくれるようなことはめったにないので、自分から何か行動をおこさないと、周囲からどんどん引き離される。(工)
- 大学での講義に出ているだけでは、授業の速度や内容の難しさから十分に理解できないことが多い。自分から学ぶ姿勢ができていないと、ただ単位を取るためだけの勉強になってしまう。(工)
【教員からのアドバイス】
- まずは高校までの一律の勉強から解放されたことを大いに喜んでください。そして、よ〜し、好きなことを思いっきりやるぞ、という気持ちが持てるといいですね。
- 目標は、最初からあるものではなく、自分でこれから見つけていくものです。何を学びたいのか、将来何をやりたいのかを見つけるために大学に入ってきたのですから、毎日積極的に授業に出てください。
- 大学の勉強は、知識だけを身につけるのではなく、学問を理解することがメインであることを自覚する。試験をパスするだけの単なる知識の詰め込みだけでは、研究を進めることはできない。学問を理解するためには、根本にある原理を十分理解することから始まり、周辺のすべての学問が必要となる。
- せっかく名大に入ったのだから、入れなかった人の分までしっかり勉強してほしい。私は以前、ある地方大学に勤めていたが、名大はとても恵まれている。