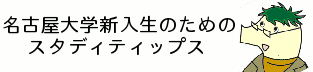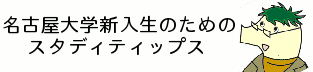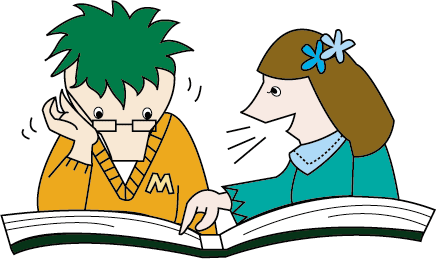大学の授業に慣れてきたら、自分がどこにつまずいたのか、なぜつまずいたのか、どのようにそれを克服したのかを振り返ってみましょう。それが、次の学習活動の改善に役立つはずです。そのためには自分の学習記録を残しておく必要があります。
大学で学習した記録を残しておきましょう。教科書、ノート、レポートなどの提出課題、ゼミでの発表資料、自分で調査した資料、取り組んだ練習問題など、さまざまな種類の学習記録が残っているはずです。これらを授業ごと、科目ごとにまとめて保存しておきましょう。資料は整理ボックスなどにまとめ、提出課題などはパソコンのハードディスクに整理しておくといいでしょう(ただし、必ずバックアップをとって、紙に打ち出しておきましょう。機械は不意に故障するものです)。
こうして集めた学習記録のことを「ポートフォリオ」と言います。ポートフォリオとはもともと、芸術家が作品を持ち運ぶために用いた挟みカバンのことでしたが、今日ではビジネス、芸術、医療、教育など諸分野における活動記録の意味で用いられています。
ポートフォリオを作っておくメリットは、自分が学んだ内容をいつでも振り返ることができるということです。結果的に、学習した内容の定着度を高めることにつながります。授業が終了したからといって、教科書や参考書を古本屋にさっさと売り払ったりしないようにしましょう。
授業でわからないところがあったら、すぐに振り返ってチェックしましょう。たとえば、基礎編の内容を理解していないと、応用編の授業を受けるときに苦労することになります。たとえば、英語の授業を苦手なままにしておくと、学部の専門授業で英語の文献を読むことができなくなってしまいます(今日の学術論文、特に理系のそれは圧倒的に英語で占められています)。また、経済学や心理学を学ぼうとする人が統計をわからないままにしておくと、後で大変苦しむことになります。授業でわからないことがあったら、その場ですぐに振り返ってチェックする方が効果的です。たとえば次のような方法があります。
- 課題の提出前には入念に推敲や見直しを行う
- 教員から試験やレポート、課題のコメントが返された時は、良かった点と悪かった点を振り返る
- 試験でできなかった問題の解答を直後に確認する
- 提出したレポートの控えをとっておき、いつでも振り返るように整理しておく
- 受講した授業の学習目標が達成できたかどうかを学期末に振り返る
- 学期末に授業評価アンケートに回答する際に、自分の学習内容を振り返る
|
ティップス21 振り返ってもわからないときは、すぐに人に聞こう
|
自分で振り返ってもなかなか理解できない時は、ためらわずに、すぐに人に聞きましょう。わからないことをそのままにしておくと、「何をわからなかったのかがわからない」ということになってしまいます。これは最悪の事態です。授業後すぐに教員やTAに聞く、あるいは一緒に受講している仲間に聞くなど、いろいろな方法があります。詳しくは、第3章「人から学ぶ」を参照して下さい。
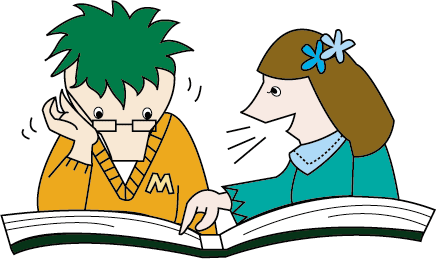
【教員からのアドバイス】
- 小生の経験からは、教員の言っていることは、その場ではまず理解できないことが多いと思います。ここからが、大学レベルの学問のおもしろさがあるわけで、その後は理解できるまで徹底的に自分で本を読んで考えるわけです。小生の経験では、同じ問題を1週間考えることができたのは、大学生の時だけです。大学院では遅いと思います。
- 聞いただけでわかる授業がよいとの風潮があります。しかし、そのような授業は、単に雑学を教えている授業か(たしかに雑談は楽しいが)、受講生に考えることを求めていない授業かもしれない。たしかに、どのようなことでも、最低覚えないといけないことはあるが(文字だって覚えなければこの文も読めない)、「覚えるだけですむ」ことは、それ以上ではない。何を言っているかわからない授業は大きな問題ではあるが、わからないと感じても、すぐにあきらめないこと。そこで言っていることを理解しようとすれば、そして理解できれば(理解できたと思った時には)、皆さんの考える力は確実に伸びています。
- 学習したということが目に見えるような工夫をしたらどうでしょう。例えば、本を読んだ後に、その本で興味深かった箇所などを抜き書きしたりしてカード化したりすると、そのカードが増えていくのは、結構楽しいもの。こうして、自分のやったことの成果のようなものを目の当たりにすると、励みになります。読んでも忘れちゃうと結構虚しいものね。つまり、学習成果を見えるようにすることが習慣を作るんじゃないかな。