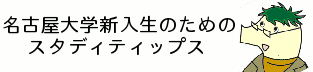
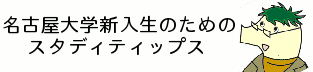
|
|
1.授業から学ぶ 1.3 まずは授業に出よう
大学で授業を受ける時は、高校との違いに誰でも最初は戸惑うものです。授業時間はとても長いし、教室も大きい。一部の科目を除けば、同じ授業は週1回しかありません。高校では同じ教室に教員が入れ替わり入ってくるのに対し、大学では学生の方が授業ごとに移動します。座席も自由です。授業ごとに受講する顔ぶれは変わります。しかも、同級生は2000人を超える大群衆です。こういう環境の中で、あなたは時として一人ぼっちになったかのような孤独感を感じることがあるかもしれません。しかし、そう感じているのはあなただけではありませんので、安心してください。誰もが最初はそうなのです。
名古屋大学のほとんどの授業は1時限90分です。高校までは1時限45〜50分の授業に慣れていたことと思います。あなたにとって、最初のうち90分という時間はとても長く感じられるかもしれません。しかし、高校よりもはるかに高度化した内容をまとまった内容として教えるためには、1回90分という時間はどうしても必要なのです。言い換えれば、1回の授業で扱う内容は、高校までの少なくとも2倍はあるということです。うっかり休んでしまうと、あとから追いつくのが大変なので、気をつけてください。最初のうちは、授業で集中力を持続するのは難しいかもしれませんが、次第に慣れてきますので、そんなに心配する必要はありません。
大学では、授業のルールの大部分は担当する教員が決めています。もちろん、基本的なことは共通です。当たり前のことですが、カンニングをしてはいけないし、私語をすれば注意されます。友だちの代わりに出席する、いわゆる「代返」も不可です。携帯電話の電源は必ず切ってください。大学では「学問の自由」が保障されている代わりに、大人として他者の人格や学習活動を尊重することが求められます。私語や携帯電話は明らかに他者の学習活動を妨害する行為です。あなたの周囲でそういう行為をしている人がいたら、注意してあげましょう。
これらの点については、各授業のシラバスを確認してください。もしくは、最初の授業の時に教員から説明があると思いますので、聞き漏らさないように注意してください。
大学の授業の基本、それは指定された教科書をちゃんと買って、専用のノートを用意して、毎回遅刻せずに出席することです。自分でお金を払って教科書を買うことによって、「さあ授業を受けるぞ」という気持ちが自然に高まってきます。なんだ、高校と同じじゃないかと思うかもしれません。そのとおりです。しかし、まじめに授業に出たとしても、大学の教員はきれいに板書してくれるとは限りません。補助プリントを配布してくれるとは限りません。試験対策を教えてくれる教員もほとんどいないでしょう。全員がわかるまで練習問題を丁寧に解説してくれるわけではありません。こうした授業に出ているうち、あなたは大学の授業はとても不親切だと感じるかもしれません。 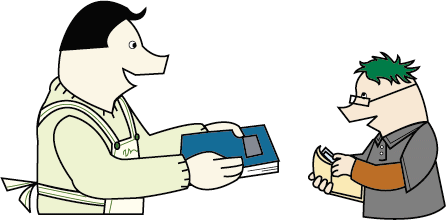
【先輩からのアドバイス】 |
戻る |