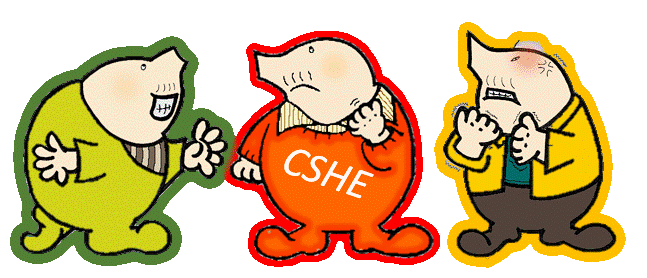准教授
Associate Professor
近田 政博
Masahiro CHIKADA
chikada@cshe.nagoya-u.ac.jp
准教授
Associate Professor
近田 政博
Masahiro CHIKADA
chikada@cshe.nagoya-u.ac.jp
2012年5月1日 改訂
■プロフィール
| 1967年 | 愛知県豊橋市生まれ |
| 1995年 | 名古屋大学大学院教育学研究科博士後期課程単位認定、名古屋大学教育学部助手 |
| 1998年 | 名古屋大学高等教育研究センター専任講師 |
| 2001年 | 文部科学省長期在外研究員としてベトナム教育発展研究院に1年間在籍(客員研究員) |
| 2003年 | 名古屋大学高等教育研究センター助教授 |
| 2006年 | 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 教育科学専攻高等教育学講座を兼担 |
| 2007年 | 名古屋大学高等教育研究センター准教授 |
- 学内兼務:
- 附属図書館研究開発室 室員、AC21推進室 室員
- 学外兼職:
- 広島大学高等教育研究開発センター 2012年度客員研究員
- 学位:
- 博士(教育学、名古屋大学、2003年1月31日)
- 所属学会:
- 日本比較教育学会(理事、紀要編集委員)、大学教育学会(理事)、日本高等教育学会、アジア比較教育学会、大学史研究会
- 賞罰:
- 日本比較教育学会 平塚賞(『近代ベトナム高等教育の政策史』多賀出版、2005年)
■専門領域
高等教育学、比較教育学
■最近の主な成果・著作物
- 名古屋大学高等教育研究センター・総務部職員課・学務部学務企画課編『名古屋大学新任教員ハンドブック』名古屋大学、2012年3月、45頁。
- 近田政博編『名古屋大学教員のための留学生受け入れハンドブック』名古屋大学高等教育研究センター、2011年3月、82頁(名古屋大学国際化拠点整備事業:非売品、高木ひとみ、田中京子、土井康裕、松浦まち子、渡部留美との共著)。
- 平成19〜21年度科学研究費補助金基盤研究(B)『研究大学の学士課程に適した優秀学生プログラムの開発に関する調査研究 成果報告書』(研究代表者:近田政博)、2010年3月、190頁。
- 夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子『大学教員準備講座』玉川大学出版部、2010年3月、221頁。
- 近田政博『学びのティップス-大学で鍛える思考法』玉川大学出版部、2009年11月、102頁。
- 近田政博『ベトナム2005年教育法』ダイテック、2009年6月、94頁(オンデマンド印刷)。
■研究課題
- 大学生のための学習支援教材の開発 (共同研究)
大学新入生が自発的・主体的に学ぶことができるようになるために、大学としてどのような学習支援が必要かについて研究しています。高等教育研究センターでは2006年3月に学内ハンドブック『名古屋大学新入生のためのスタディティップス』を刊行しました。このスタディティップスは『「学識ある市民」をめざして』と『学問を始めよう』の2冊から構成されています。『「学識ある市民」をめざして』では、大学で学ぶことの意味と大学で学ぶための倫理・ルールについて解説しました。『学問を始めよう』では、大学で学ぶための具体的な方法・アイデアを示し、学内の教員や上級生が蓄積してきた学びの知恵・ノウハウを示しました。
このスタディティップスは毎年内容の改訂を行っています。2007年版では実験授業に関するノウハウを追加し、2008年版では学内の各種コンテストや大学院に関する情報などをコラムで追加しました。2009年秋には、近田の責任執筆で内容を全面改訂し、書籍版として玉川大学出版部から刊行しました。
また、このスタディティップス制作のための基礎研究として、世界各国の研究大学における優秀大学プログラム(いわゆるオナーズ・プログラム)について調査を行いました(科研基盤B:下記参照)。2007年度は上海交通大学、トロント大学、スタンフォード大学、イングランドの諸大学、2008年度はワシントン大学、テキサス大学、グリフィス大学(オーストラリア)、エジンバラ大学などを調査しました。2009年にはその成果を高等教育学会で共同発表しました。
2011年度は、附属図書館研究開発室の室員を兼務し、学士課程におけるアカデミック・ライティング支援に関するセミナーを担当しました。2012年度は文系基礎科目「学術論文の書き方入門」のオリジナルテキスト(下記)を共同制作し、これを用いて学部1年生130人の大規模授業において「書くスキル」をどのように高めることができるかにチャレンジしています。
- 【主要著作】
-
- Paul W. L. Lai原作、近田政博編集・訳『Mei-Writing 日本語版 論理的に書く技法(初版)』(平成24年度全学教育文系基礎科目「学術論文の書き方入門」テキスト)、2012年、42頁
- 近田政博『学びのティップス 大学で鍛える思考法』玉川大学出版部、2009年、102頁。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋大学新入生のためのスタディティップス』ウェブ版、2008年12月31日改訂。
- 【主要な研究費】
- 平成19〜21年度科学研究費補助金基盤研究(B)「研究大学の学士課程に適した優秀学生プログラムの開発に関する調査研究」(研究代表者:近田政博)
- 大学院での研究指導方法(個人研究)・大学院での学習・研究方法(共同研究)
これまで大学院における研究指導方法はベールに覆われた存在でした。個々の指導教員と大学院生のパーソナルな関係に大きく依存し、研究指導方法の標準化・体系化や知見の共有はほとんど行われてきませんでした。6千人の大学院生を擁する名古屋大学にとって、この問題は緊急性と重要性を増しています。すでに欧米諸国では大学院研究指導のさまざまなノウハウの蓄積があります。平成19年度は、オーストラリアのメルボルン大学が1999年に制作した研究指導のためのハンドブック(Eleven Practices of Effective Postgraduate Supervisors)の翻訳を行いました。平成20年度は、名古屋大学における研究指導の実態についてのインタビュー調査を実施し、論文にまとめました。
平成21年度は、当センターの共同事業として『ティップス先生からの7つの提案』大学院生編の制作を行いました。平成22年度は、留学生の受け入れにおいて名古屋大学の教員がどのような課題を抱えているかについて学内研究会を組織してアンケート調査を実施し、グローバル30事業費によって『名古屋大学教員のための留学生受け入れハンドブック』を作成しました。
- 【主要な研究費】
- 平成19〜21年度科学研究費補助金基盤研究(B)「研究大学の学士課程に適した優秀学生プログラムの開発に関する調査研究」(研究代表者:近田政博)
- 平成24〜26年度科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「社会人大学院生の学習特性・環境に適した教授法と研究指導方法の開発」(研究代表者:近田政博)
- 【主要著作】
-
- 近田政博編『名古屋大学教員のための留学生受け入れハンドブック』名古屋大学高等教育研究センター、2011年3月、82頁(名古屋大学国際化拠点整備事業:非売品、高木ひとみ、田中京子、土井康裕、松浦まち子、渡部留美との共著)。
- 近田政博「留学生の受け入れに関する大学教員の認識」『名古屋高等教育研究』第11号、2011年、191-210頁(査読有)。
- 近田政博「大学院の研究指導方法に関する課題と改善策−名古屋大学教員に対する面接調査結果より−」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第9号、2009年、93-111頁。
- リチャード・ジェームス、ガブリエル・ボールドウィン(近田政博訳)『研究指導を成功させる方法−学位論文の作成をどう支援するか−』2008年、61頁。
-
ベトナム高等教育政策に関する研究(個人研究)
私はもともと比較教育学という分野の研究者で、特にベトナム高等教育の歴史的な形成過程を研究してきました。歴史をひもとくと、多くの発展途上国の高等教育は政治状況に大きく依存してきました。ベトナムの場合、植民地経験、南北対立、社会主義化、市場経済化という大きな変動を経験してきました。高等教育はそのつど政治変動から大きな影響を受け、特定の外国の教育モデルに支配されてきました(中国、フランス、ソ連など)。21世紀を迎えて、ベトナムの高等教育政策は「量的拡大」から「質的充実」に方向転換しようとしています。
2007年2月にはベトナム・ホーチミン市国家大学社会・人文科学大学において教員・大学院生のための教授法研修会を実施しました。その結果を教育・学習セミナー(2008年2月)でフィードバックしました。日本で培ったFDの方法論がベトナムでどのように適用できるのかについて比較教育学の観点から研究しました。
また、ベトナムでは1998年に策定された教育法が2005年に大幅改訂されました。今日のベトナムは、市場化に伴って多様化しつつある教育の質をどう管理し、向上させるかに大きな関心を持っています。2005年教育法では95年教育法のどの部分がどのように改訂されたのか、それがどのような意味を持つのかを検討しました。
- 【主要な研究費】
- 平成18〜20年度科学研究費補助金萌芽研究「市場経済移行期のベトナムにおける大学教授法研修プログラムの開発研究」(研究代表者:近田政博)
- 【主要著作】
-
- 近田政博訳『ベトナム2005年教育法』、2009年6月、ダイテック。
- 近田政博『近代ベトナム高等教育の政策史』多賀出版、2005年。
- 近田政博『近代ベトナム高等教育の形成過程に関する研究−外国教育モデル受容の比較教育学的分析−』名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士学位論文(論文博士)、2003年2月審査合格、300頁。
■メッセージ
学生にとっても、教師にとっても、名古屋大学がもっと魅力的な存在になるためにはどうしたらよいかを日々考えています。特に、大学生が主体的・自発的に学ぶようになるために大学がどのような支援をしたらよいのかについて研究しています。仕事は大きく二つです。一つは教育・学習効果を高めるための各種支援教材を開発し、普及させること、もう一つは学内外のFD・SD活動です。前者はコツコツ進めていますが、後者は試行錯誤の連続です。また、比較教育学の研究者としてはベトナム高等教育改革について定点観測を行っています。
プライベートでは小6の娘と小3の息子の子育てを楽しんでいます。横着でいいかげんな父親ですが、子育ては発見と感動の連続です。趣味は温泉めぐりと同僚教員のものまねです。週末はアマチュアオーケストラでバイオリンを弾きます。仕事以上に必死に練習しているという自負があります。
■活動データ
●教育活動 (平成24年度)
<大学院課程>
- 「高等教育基礎論−研究方法」(教育発達科学研究科、前期2単位)木曜6限
- 「高等教育内容論−学修支援・FD」(教育発達科学研究科、後期2単位)木曜6限
- 「リサーチスキル」(教育発達科学研究科、前期2単位)一部分を担当
<学士課程>
- 「学術論文の書き方入門」(全学教育、文系基礎科目、前期2単位)木曜2限
- 「現代社会と教育」(全学教育、文系教養科目、後期2単位)水曜3限
- 「医学入門」(医学部医学科1年生、前期2単位、「レポートの書き方」を担当)
<大学院ゼミ>
- 平成24年度はD3:1人、D1:1人、M2:3人、大学院研究生:1人、(合計6人)
- 2010年8月27〜28日 地獄のゼミ合宿(愛知県幡豆町)

- 2011年8月20日 地獄のゼミ合宿(長野県昼神温泉)

●最近の研究活動
<著書 (*印以外は購入可)>
- 名古屋大学高等教育研究センター・総務部職員課・学務部学務企画課編『名古屋大学新任教員ハンドブック』名古屋大学、2012年3月、45頁。(*)
- 近田政博編『名古屋大学教員のための留学生受け入れハンドブック』名古屋大学高等教育研究センター、2011年3月、82頁(名古屋大学国際化拠点整備事業:非売品)(*)
- 名古屋大学高等教育研究センター編『ティップス先生からの7つの提案(大学院生編)』2011年(オンデマンド印刷)、12頁。
- 夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子『大学教員準備講座』玉川大学出版部、2010年3月、221頁。
- 近田政博『学びのティップス-大学で鍛える思考法』玉川大学出版部、2009年11月、102頁。
- 近田政博『ベトナム2005年教育法』ダイテック、2009年6月、94頁(オンデマンド印刷)。
- *名古屋経済学教育研究会『経済学英語ハンドブック−授業で使える例文集』ダイテック、2009年、42頁(オンデマンド印刷)。
- 中井俊樹編『大学教員のための教室英語表現300』アルク、2008年、94頁(共著の一人)。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋大学新入生のためのスタディティップス1−「学識ある市民」をめざして』2008年。(*)
- 名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋大学新入生のためのスタディティップス2−学問を始めよう』2008年。(*)
- 名古屋大学高等教育研究センター編『ティップス先生のカリキュラムデザイン』2007年(オンデマンド印刷)、73頁。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『ティップス先生からの7つの提案(教務学生担当職員編)』2007年(オンデマンド印刷)、12頁。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『ティップス先生からの7つの提案(IT活用授業編)』2006年(オンデマンド印刷)、12頁。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『ティップス先生からの7つの提案(教員編、学生編、大学編)』2005年(オンデマンド印刷)、12頁。
- 近田政博『近代ベトナム高等教育の政策史』多賀出版、2005年、418頁。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『プロフェッショナルスクールのための授業設計ハンドブック』(非売品)、 2004年、65頁。(*)
- 池田輝政・戸田山和久・近田政博・中井俊樹 『成長するティップス先生−授業デザインのための秘訣集』玉川大学出版部, 2001年、186頁。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『ティップス先生からの7つの提案(教員編、学生編、大学編)』2005年(オンデマンド印刷)、12頁。
<訳書>
- (英語)リチャード・ジェームス、ガブリエル・ボールドウィン(近田政博訳)『研究指導を成功させる方法−学位論文の作成をどう支援するか−』2008年、61頁。
- (ベトナム語)近田政博訳『ベトナム2005年教育法』、2009年6月、ダイテック。
<論文・分担執筆など>
- 近田政博「留学生の受け入れに関する大学教員の認識」『名古屋高等教育研究』第11号、2011年、191-210頁(査読有)。
- 近田政博「比較教育学研究のジレンマと可能性−地域研究再考」『比較教育学研究』第42巻、2011年、111-123頁(全国学会誌、依頼論文)。
- 近田政博・鳥居朋子「優秀学生を対象とした特別教育プログラムの日米比較−学士課程におけるオナーズプログラムに注目して」『大学教育学会誌』第32巻、第1号、2010年、85-93頁(全国学会誌、査読有)。
- 近田政博「大学院の研究指導方法に関する課題と改善策−名古屋大学教員に対する面接調査結果より−」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第9号、2009年、93-111頁(査読有)。
- 安田淳一郎・近田政博「教育改善活動に参加する学生の意識変化−名大物理学教室における学生教育委員会の事例−」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第9号、2009年、113-132頁(査読有)。
- 近田政博「社会人大学院生を対象とする研究方法論の授業実践」『名古屋高等教育研究』第8号、2008年、73-94頁(査読有)。
- 近田政博・戸田山和久・夏目達也・中井俊樹・鳥居朋子「大学での学びを促進する全学新入生向け教材の開発」『名古屋高等教育研究』第7号、2007年、125-145頁(査読有)。
- 近田政博「研究大学の院生を対象とする大学教授法研修のあり方」『名古屋高等教育研究』第7号、2007年、147-167頁(査読有)。
- 黒田光太郎・速水敏彦・浜田道代・近田政博・夏目達也「全学教育FDの軌跡と今後の方向性」『名古屋高等教育研究』第7号、2007年、67-77頁。
- 近田政博「現代ベトナムの教育計画」杉本均・山内乾史編『現代アジアの教育計画』学文社、2006年、236-253頁(査読有)。
- 中井俊樹・中島英博・近田政博「名古屋大学の教育の質向上に有効な教員・学生・大学組織の実践手法−『優れた授業実践のための7つの原則』のチェックリストを用いた調査−」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第6号、2006年、77-92頁(査読有)。
- 近田政博「基礎セミナー『他人について調べて書く技法を身につける』の実践−体験型授業をめざして」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第5号、2005年、65-83頁(査読有)。
- 近田政博「ベトナム 高等教育100万人時代の質保証」馬越徹編著『アジア・オセアニアの高等教育』玉川大学出版部、2004年、124-148頁。
- 近田政博「初年次教育の日米比較−特質と課題」『大学教育学会誌』第26巻第1号、2004年、44-49頁。
- 中島英博、中井俊樹、近田政博、鳥居朋子、池田輝政「『ゴーイングシラバス』を通して見える新しい授業空間−授業マネジメントツールの開発と教育改善効果」名古屋大学高等教育研究センター『名古屋高等教育研究』第3号、2003年、67-81頁。
- 近田政博『近代ベトナム高等教育の形成過程に関する研究−外国教育モデル受容の比較教育学的分析』名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士学位請求論文、300頁(2003年2月審査合格)。
<主な報告書論文>
- 近田政博「オーストラリア高等教育研究開発学会(HERDSA)発表者に対するアンケート調査結果」『学生・教師の満足度を高めるためのFD組織化の方法論に関する調査研究』平成16〜17年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書(研究代表者:夏目達也)、2006年、203-214頁。
- 名古屋大学高等教育研究センター編『初年次オリエンテーションを支援するスタディティップスの開発と活用に関する事業』成果報告書(平成16年度学生支援特別経費)(研究代表者:近田政博)、2005年。
- 近田政博・鳥居朋子「名古屋大学におけるFDの状況」『大学におけるFD・SD(教員職員資格開発)の制度化と質的保証に関する総合的研究』平成14〜16年度日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究(A)(1))研究成果報告書(研究代表者:有本章)、2005年、220-227頁
- 近田政博「現代ベトナムの高等教育戦略−量の拡大から質の追求へ」『アジア諸国におけるグローバリゼーション対応の高等教育改革戦略に関する比較研究』平成14〜15年度科学研究費補助金基盤研究(B)(1)研究成果報告書(研究代表者:大塚豊)、2004年、130- 155頁。
<主な翻訳>
- (英語)ブルース・マクファーレン「知的指導者としての大学教授」平成22〜24年度科学研究費補助金(基盤研究B)『大学経営高度化を実現するアカデミック・リーダーシップ形成・継承・発展に関する研究』中間報告書(研究代表者:夏目達也)、2012年、109-135頁。
- (英語)スコット・イーヴンベック、バーバラ・ジャクソン「FD(ファカルティ・ディベロップメント)と初年次教育」『初年次教育ハンドブック−学生を「成功」に導くために』(山田礼子監訳)丸善、2007年、79-102頁。
- (英語)モハメッド レザ・サルカール アラニほか「イランにおける教育行政官の専門能力開発に関する事例研究−働くために学ぶ、学ぶために働く:現職学習の実践手法−」『名古屋高等教育研究』第6号、2006年、195-214頁。
- (英語)C.マッチ「高校生から大学生への移行−諸文献、教員、成功した学生からのアドバイスの分析」名古屋大学高等教育研究センター編『初年次オリエンテーションを支援するスタディティップスの開発と活用に関する事業』(平成16年度学生支援特別経費成果報告書)、2005年、15-33頁。
- (英語)D.グロスマン「日本と香港の教員養成」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第4号、2004年、127-145頁。
- (英語)K.モーガン「英国の大学における質の評価」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第3号、2003年、111-136頁。
- (ベトナム語)「ベトナム民立大学規則」『アジア諸国における中等・高等教育の民営化に関する実証的比較研究−その特質と問題点に関する考察−』平成13〜14年度科学研究費補助金基盤研究(B)(1)研究成果報告書(研究代表者:村田翼夫)、2003年、89-102頁。
- (ベトナム語)「ベトナム教育法」名古屋大学高等教育研究センター編『名古屋高等教育研究』第1号、2001年、183-220頁。
<書評>
- P.G.アルトバック、馬越徹編(北村友人監訳)『アジアの高等教育改革』玉川大学出版部(所収『IDE現代の高等教育』2007年11月号、63-64頁)。
<研究発表等>(予定分を含む、2003年以降)
- 近田政博「アカデミックライティングをどう組織化するか−『名古屋大学学生論文コンテスト』の事例を中心に−」大学教育学会第34回大会、北海道大学、2012年5月27日。
- Chikada, M., “Social Responsibilities for University Administrators: from bureaucrats to academics”, in 2nd Asia-Europe Education Workshop, hosted by Asia-Europe Foundation, June 4, 2011.
- 近田政博「留学生の受け入れに関する大学教員向けガイドの開発とその有効性」日本高等教育学会第14回大会、2011年5月28日。
- 近田政博「名古屋大学における大学教員準備講座の取り組み」『第17回大学教育研究フォーラム特別企画ラウンドテーブル』京都大学、2011年3月18日。
- Coverdale-Jones, T., Chikada, M., “Lecturers’ Perceptions of Teaching International Students”, presentation at Academic Consortium21, Shanghai, China, 19 Oct 2010.
- 近田政博、公開シンポジウム「比較教育学と国際教育開発」のコメンテーター、日本比較教育学会、2010年6月27日。
- 近田政博・勢村かおり「ベトナムにおける2005年教育法と98年教育法の比較考察−教育の質を法律によってどう担保するか」第45回日本比較教育学会で共同発表、2009年6月27日
- 井下千以子・長澤多代・土持法一・近田政博「ライティング教育を基点にした学習支援とFD 活動の展開」第31回大学教育学会のラウンドテーブル発表、2009年6月6日
- 近田政博・鳥居朋子・佐藤万知・中島夏子「学士課程教育の質的向上におけるオナーズプログラムの役割」第12回日本高等教育学会、2009年5月23日
- Chikada, M., “Support for Teaching and Learning at Nagoya University”, International Conference on Business, Economics and Information Technology, Nagoya City, Japan, March 9, 2009
- 近田政博「近代ベトナムにおける外国大学モデルの選択と受容」大学史研究会第31回研究セミナー・シンポジウム、 2008年12月20日
- Chikada, M., “The Development in Teaching and Learning at Japanese Research Universities”, AC21 International Forum 2008, at North Carolina State University, July 28, 2008
- 近田政博「ホーチミン市国家大学における教育・学習セミナーの実施と課題」第44回日本比較教育学会、2008年6月28日
- 近田政博「大学院における研究指導の実践手法に関する考察−メルボルン大学研究指導ハンドブックの日本への適用可能性−」第11回日本高等教育学会、2008年5月23日
- Chikada, M., “The Dilemma in Japanese School Curriculum”イラン教育省での教育改革国際シンポジウム、2008年4月27日
- 近田政博「ベトナムにおける大学教授法研修会の可能性と有効性」第43回日本比較教育学会、2007年6月30日
- 近田政博「高等教育研究における開発型アプローチの可能性と課題」日本教育工学会シンポジウム、2007年6月16日
- 近田政博「名古屋大学における大学院生向けの大学教員準備プログラム」第29回大学教育学会ラウンドテーブル、2007年6月9日
- 近田政博・夏目達也「大学院生を対象とした大学教授法研修会の可能性と課題」、第10回日本高等教育学会、2007年5月26日。
- 近田政博「教育スキルをもった大学院生をみんなで育てよう!−TA養成から院生育成へ−」第2回大学教育改革フォーラムin東海、2007年3月10日
- 中井俊樹、夏目達也、近田政博、鳥居朋子、青山佳代、中島英博「教員・学生・大学組織の相互関係を重視した教育の質向上の具体的方法」第28回大学教育学会、2006年6月11日。
- 近田政博、夏目達也、中井俊樹、鳥居朋子「大学コミュニティへの適応を促進する新入生向け学習支援教材の開発−『名古屋大学新入生のためのスタディティップス』の事例より−」第28回大学教育学会、2006年6月11日。
- 近田政博「『大学でどう学ぶか』を学ぶ授業実践とその課題」第27回大学教育学会、2005年6月11日。
- 中井俊樹、中島英博、近田政博「学生の学習参加度を高めるための学生・教員・大学の役割−「優れた授業実践のための7つの原則」の適用可能性に関する考察」第8回日本高等教育学会、2005年5月21日。
- 黒田光太郎、近田政博、夏目達也、鳥居朋子「新しい教養教育実施組織下での授業実践の課題−名大教養教育院における授業評価アンケートとその活用−」第8回日本高等教育学会、2005年5月21日。
- 鳥居朋子、中島英博、近田政博「社会人学生に有効な授業設計の方法論」第7回日本高等教育学会、2004年7月25 日。
- 近田政博「初年次教育におけるスタディティップスの位置づけ−名古屋大学の取り組み」第26回大学教育学会、 2004年6月12日。
- 近田政博「初年次教育の日米比較−特質と課題」大学教育学会課題研究集会シンポジウム、2003年11月30日。
- 近田政博・中井俊樹・池田輝政「学習ポートフォリオを用いた授業改善−「ゴーイングシラバス」の活用と改訂を通して」日本高等教育学会第6回大会、2003年。
<学外での招聘講演・研修活動(2005年〜)>
東海地区大学協議会図書館実務担当者研修会(2012年)、自民党愛知県連(2012年)、名古屋市立向陽高等学校(2012年)、名古屋大学生協(2012年)、立命館大学(2012年)、修文大学(2012年)、ASEM教育ワークショップ(2011年)、名大祭実行委員会(2011年)、愛工大名電高等学校(2011年)、名古屋大学附属中・高等学校(2011年)、電通育英会(2011年)、名古屋市立向陽高等学校(2011年)、札幌医科大学(2011年)、立教大学(2011年)東海地区大学図書館協議会(2011年)、京都大学 大学教育研究フォーラム(2011年)、立命館大学(2011年:3回)、名古屋市立大学(2011年)、名古屋市立向陽高校(2010年)、産業医科大学(2010年)、北里大学(2010年)、長野県飯田市役所(2010年)、星城大学(2010年)、桜美林大学(2009年)、筑波大学(2009年)、四日市看護医療大学(2009年)、愛知県立芸術大学(2009年)、北里大学(2009年)、名古屋市立大学(2009年)、名古屋市立向陽高等学校(2009年)、関西国際大学(2009年)、同朋大学(2009年)、愛知県立看護大学(2008年)、関西大学(2008年)、愛知淑徳大学(2008年)、北陸先端科学技術大学院大学(2008年)、北里大学(2008年)、名古屋市立大学(2008年)、イラン教育省・科学研究技術省(2008年)、静岡文化芸術大学(2008年)、大阪樟蔭女子大学(2008年)、愛知産業大学(2008年)、ベトナム・ホーチミン市社会・人文科学大学(2008年)、名古屋市立大学(2007年)、愛知淑徳大学(2007年)、愛知東邦大学(2007年)、石川県立大学(2007年)、静岡県西部高等教育ネットワーク会議(2007年)、第2回大学教育改革フォーラム(2007年)、ベトナム・ホーチミン市社会・人文科学大学(2007年)、同志社大学(2006年)、桜美林大学(2006年)、大阪工業大学(2006年)、静岡大学(2006年)、関西国際大学(2006年)、愛知県准看護師養成所教務主任等研修会(2006年)、九州大学(2006年)、第1回大学教育改革フォーラム(2006年)、豊橋技術科学大学(2006年)、岩手県立大学(2005年)、愛知県准看護師養成所教務主任等研修会(2005年)、日本私立大学連盟(2005年)、早稲田大学(2005年)、神戸学院大学(3回:2005年)、佛教大学(2005年)、大学コンソーシアム京都(2005年)、南京師範大学(中国:2005年)
招聘講演のテーマ:大学教授法、授業デザイン論、FDマネジメント論、学習支援論、初年次教育論、大学院研究指導、アカデミック・ライティング支援、留学生支援、大学職員論など。
●その他の活動
- 豊橋交響楽団 団員(バイオリン)